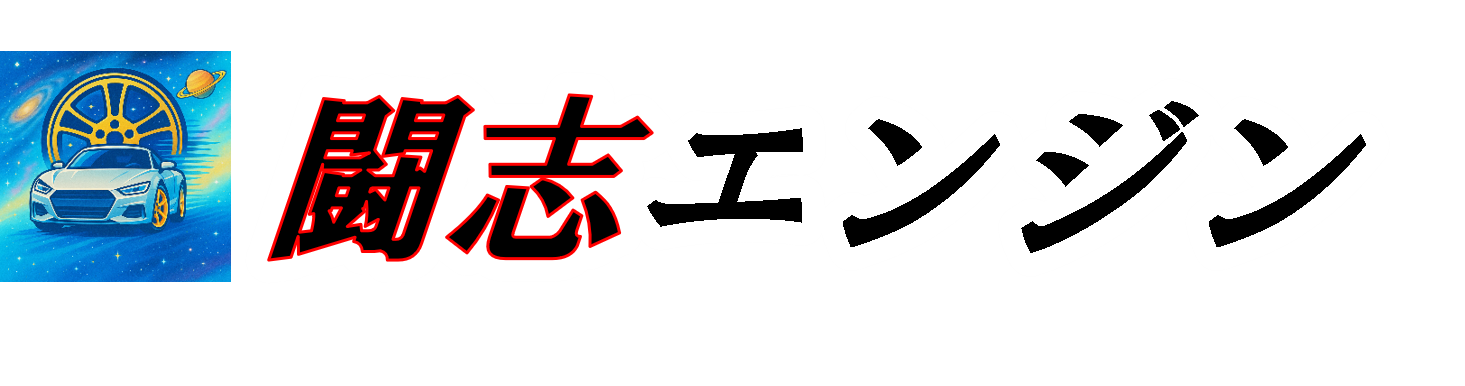日産・GT-R「R35型」の生産終了と歴史

本記事は広告を含みます。
日産は代表的なスポーツカーとして「GT-R」を手掛けていましたが、とうとうR35型の生産終了のアナウンスが実施されました。そこで本記事では日産のスポーツカー史とともにGT-Rの生産終了の詳細について解説します。
日産が生み出したスポーツカーの歴史

日産自動車は、その長い歴史の中で数多くのスポーツカーを世に送り出してきました。特に「スカイライン」シリーズは、日本国内外で高い評価を受けています。1969年に登場した初代「スカイラインGT-R」は、レースシーンでの活躍もあり、一躍その名を轟かせました。その後、1989年に復活した「R32型GT-R」は、先進的な技術と圧倒的な性能で「ゴジラ」の愛称で親しまれ、世界中の自動車ファンを魅了しました。日産のスポーツカーの歴史は、1950年代にまで遡ります。1952年に登場した「ダットサン・スポーツDC-3」は、日産初のスポーツカーとして知られています。その後、1960年代には「フェアレディ」シリーズが登場し、特に1969年に発売された「フェアレディZ(S30型)」は、北米市場で大ヒットを記録しました。このように、日産は常にスポーツカーの分野で革新を続け、多くの名車を生み出してきました。
日産GT-Rの生産終了と重要ポイント

2024年3月14日、日産はR35型GT-Rの2025年モデルを発表し、同時に2025年8月をもって生産を終了することを正式に発表しました。これにより、2007年のデビュー以来18年間にわたるR35型の歴史に幕が下ろされることとなりました。この決定は、多くのGT-Rファンにとって衝撃的なニュースとなりました。2025年モデルでは、「GT-Rプレミアムエディション」に青を基調とした専用特別内装色「ブルーヘブン」が新たに設定されました。また、「GT-RプレミアムエディションTスペック」と「GT-Rトラックエディションengineered by NISMO Tスペック」には、高精度重量バランス部品が採用され、エンジンのレスポンス精度が向上しています。これらのモデルには、赤文字で匠の名が刻まれたアルミ製ネームプレートと、ゴールドのモデルナンバープレートがエンジンルーム内に設置されています。生産終了の背景には、環境規制の強化や部品供給の問題が挙げられます。特に、2007年の誕生から17年が経過し、サプライヤーからの供給が難しい部品が多く出ていることが、生産終了の大きな要因となっています。
日産GT-Rの歴史

初代GT-R(1969年-1973年)
初代GT-Rは、1969年に「PGC10型」として4ドアセダンで登場し、翌年には2ドアクーペの「KPGC10型」が追加されました。2.0リッター直列6気筒エンジンを搭載し、レースでの活躍により高い評価を得ました。特に、国内レースでの連勝記録は、GT-Rの名声を高める要因となりました。
第二世代GT-R(1989年-2002年)
16年の沈黙を破り、1989年に「R32型GT-R」が登場しました。先進の4WDシステム「ATTESA E-TS」や4輪操舵システム「SUPER HICAS」を搭載し、レースシーンで圧倒的な強さを誇りました。その後、R33型、R34型と進化を遂げ、GT-Rの名声を不動のものとしました。
R35型GT-R(2007年-2025年)
2007年に登場したR35型GT-Rは、従来のスカイラインの名を外し、独立したモデルとしてデビューしました。3.8リッターV6ツインターボエンジンを搭載し、当初は480馬力を発揮。その後の改良で最終的には600馬力に達しました。また、先進のトランスミッションや高性能なシャシーにより、スーパーカーキラーとしての地位を確立しました。R35型は、デビュー以来数多くの改良が施されてきました。2010年のマイナーチェンジでは、エンジン出力の向上やサスペンションの改良が行われ、2016年には内外装のデザイン変更やインフォテインメントシステムの刷新が実施されました。さらに、2023年のフェイスリフトでは、フロントバンパーやリアバンパーのデザインが一新され、空力性能の向上が図られました。
日産GT-Rが生産終了する理由

GT-Rの生産終了の背景には、主に以下の要因が挙げられます。
規制の強化

近年、各国で環境規制や安全基準が厳格化されており、GT-Rの現行モデルがこれらの新しい基準を満たすことが難しくなっていました。とくに欧州や北米市場では、CO2排出量の厳格な制限が導入され、自動車メーカーにとってガソリンエンジン車の開発・販売が年々困難になっています。R35型GT-Rのパワートレインは非常に高性能ですが、そのぶん排出ガス量も少なくなく、新基準への適合が現実的に難しくなったことが、生産終了の大きな理由の一つです。また、安全性に関する規制も無視できません。自動ブレーキや車線維持支援などの先進運転支援システムの装備が義務化されつつある中で、R35型GT-Rには当初から設計に含まれていないこれらの装備を後付けするのは、技術的にもコスト的にも現実的ではありません。これまでGT-Rが長年にわたり改良を重ねてきたとはいえ、2007年の基本設計をベースとしていることから、新しい技術への対応には限界があったのです。
サプライチェーンの問題

さらに、サプライチェーンの問題も生産終了に影響しています。GT-Rは手作業によるエンジン組み立てなど、非常に高度な製造工程を必要とするモデルであり、使用される部品も専用の高精度なものが多くあります。しかし、時代とともにそれらの部品の供給が困難になってきており、生産の継続が難しくなったという事情もあります。日産としても、GT-Rという象徴的なモデルを簡単に手放すことは望んでいなかったと考えられますが、規制や供給体制、そして企業全体の電動化への舵取りを優先する必要性から、このような苦渋の決断に至ったのでしょう。
日産の今後のスポーツカー活動とユーザーの期待

日産GT-Rの生産終了というニュースは、世界中のスポーツカーファンに大きな衝撃を与えましたが、これは終わりではなく、新しい始まりでもあると捉えるべきかもしれません。GT-Rというブランドは、単なる車名以上の意味を持ちます。それは日産の技術力、走りへの情熱、そして日本の自動車文化の象徴とも言える存在です。近年、日産はZシリーズの復活やEV戦略に注力しており、スポーツカーと電動化を両立する道を模索しています。例えば、2022年に発表された新型「フェアレディZ(RZ34型)」は、内燃機関を残しつつも現代的なデザインと走行性能を融合させ、多くの注目を集めました。このような動きから見ても、日産がスポーツカー市場を今後も見据えていることは明らかです。GT-Rの後継となる新型モデルが登場する可能性は十分にあります。実際、2021年には日産が「次世代GT-Rは電動化されるだろう」と公式に示唆したこともありました。将来的には完全な電動スーパースポーツカーとして生まれ変わる可能性もあり、その時にはGT-Rがまた新たな伝説を作り出すことになるでしょう。ユーザーとしては、GT-Rに求めるのは単なる速さだけでなく、そのブランドが持つストーリーや情熱です。たとえパワートレインが変わろうとも、GT-Rのスピリットが受け継がれる限り、その魅力は不変です。エンジン音がなくても、かつてのGT-Rと同じように、ドライバーの心を揺さぶる車であってほしいというのが、多くのファンの共通した願いでしょう。また、日産がGT-Rを支えてきたファンやオーナーに対して、しっかりとアフターサポートを提供し続けることも重要です。パーツ供給の継続や、メンテナンス体制の充実は、ブランドの信頼性に直結します。GT-Rという車を通して築かれてきた信頼関係を今後も維持し、次世代へとつなげていくことが、日産にとって最大の使命と言えるでしょう。
まとめ

日産GT-Rは、その登場から現在に至るまで、常に時代の最先端を走り続けてきた車です。単なるスペックだけでなく、テクノロジーと情熱が融合した存在として、多くの人々の心を魅了してきました。そのGT-Rがついに生産終了を迎えるというニュースは、自動車業界における一つの時代の終わりを意味しています。しかし、これはあくまでも「R35型GT-R」の終了であり、GT-Rという名そのものが消えるわけではありません。日産の開発陣が培ってきた技術や思想は、次なるモデルに引き継がれていくでしょう。電動化という時代の大きな流れの中で、GT-Rがどのように再構築されるのか、それを見守ることが今後の楽しみでもあります。ファンの間では、GT-Rという存在が持つ「神格化された魅力」に対する深い愛着があります。それは、スペックシートでは表せない、ドライバーと車の間にある「絆」のようなものです。R35が生産を終えた今、その想いがさらに強くなるのは間違いありません。これからのGT-Rが、どのような姿で戻ってくるのか。ガソリンエンジンを失っても、音や振動が変わっても、GT-RがGT-Rである限り、多くの人々の心を動かす存在であり続けることでしょう。日産には、そんな未来を期待しています。GT-Rの伝説は、これからも終わることなく、続いていくのです。
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説