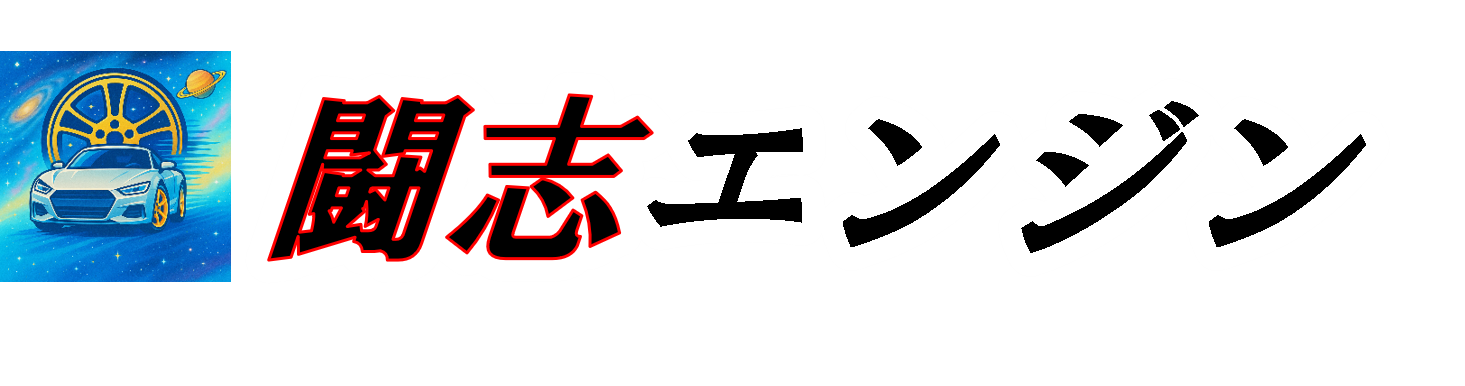日産・スポーツカーのカタログ馬力と実馬力の比較

本記事は広告を含みます。
皆さんは車の馬力についてどうお考えでしょうか?馬力は車のスペックをアピールするポイントのひとつであり、重要視している方も多いと思います。そこで今回は日産・スポーツカーのカタログ馬力と実馬力について比較したいと思います。日産は長年にわたり、多くの魅力的なスポーツカーを世に送り出してきました。GT-RシリーズやフェアレディZ、180SX、シルビアなどは国内外で高い評価を受けており、今でも語り継がれます。これらの車両は卓越した性能と独自のデザインで、多くのファンを魅了してきたでしょう。
スカイラインGT-R 32型

R32型スカイラインGT-Rは1989年に登場し、日産の「901運動」の集大成として開発されました。2ドア・クーペで当時の最新技術を結集したモデルです。特に電子制御トルクスプリット4WDシステム「アテーサ E-TS」や、4輪操舵システム「スーパーハイキャス」など、先進的な技術が採用されており、高い運動性能を実現しています。カタログ馬力は280馬力であり、実馬力では300馬力とされています。600馬力を想定して作成されたとも言われており、RBエンジンの完成度の高さに驚かされます。トヨタがJZエンジンとなれば、日産の対抗馬はRBエンジンだったことは言うまでもありません。レースでは、1990年シーズンの全日本ツーリングカー選手権でデビューを果たし、デビューウィンを飾ります。その後も93年に全日本ツーリングカー選手権のグループA規定での開催が終わりを迎えるまで29戦29勝を達成しました。あまりにも驚異的な性能だったため、GT-RにはGT-Rでしか勝てないと言われました。
スカイラインGT-R 33型


R33型スカイラインGT-RはR32の後継モデルとして登場しました。ベース車のサイズアップにより、全長が延長され、居住性が向上しています。しかし、その大型化により、当時のファンからは賛否が分かれました。一方で、シャシー剛性の向上や、サスペンションの改良などにより、走行性能は確実に進化しています。カタログ馬力は280馬力ですが、実馬力では320馬力とされています。チューニング性が極めて高いことから、500馬力程度まではあっという間にパワーアップすることができました。先代と比較すると全長が130ミリ・ホイールベースも105ミリに拡大され、居住性が良くなりました。ホイールベースが延長されどっしりと構えたボディーは安定感を生み、高速走行においても優れていました。「高性能」と「高い居住性」を融合した理想的な車だったと言っても過言ではありません。しかし、見た目のことや某峠漫画の評価が相まって不評となってしまったのは残念なことです。スカイラインGT-Rとして正統進化と言えるモデルでしたが、当時では世間の認識は厳しいものでした。
スカイラインGT-R 34型

R34型スカイラインGT-Rは最後のスカイラインGT-Rであり、映画「ワイルドスピード」にも登場したことで人気が向上しました。エンジンは直列6気筒ツインターボ「RB26DETT」を搭載し、ブラッシュアップされた性能を発揮します。カタログ馬力は280馬力、実馬力では340馬力とされ、先代のR33の弱点であった低回転でのもたつきが改善されました。R34型は欧州メーカーとなるBMWやメルセデスベンツのセダンをライバル視しており、ボディー剛性が強化されました。またホイールベースの短縮などにより、スポーツドライビングの楽しさが向上しています。ボールベアリングを備えたセラミックタービン、ゲトラグ製の6速MTなどが採用されたほか、コンソール中央に車両の状態を確認する5.8インチのモニターが搭載され、水温、ブースト圧などがモニターで確認できるのは斬新な発想でした。人気モデルとしてニュルなどがありますが、やはり外せないのは「Zチューン」でしょう。ニスモが手掛けたコンプリートカーであり、19台の限定販売でした。走行距離3万キロ以下のユーズドカーをベースに車体はバラバラに分解した上で、新たにボディー補強などを施しながらハンドメイドで組み立てられています。専用チューンされた2.8リッターのRBエンジンは500馬力を発揮し、伝説的な存在になっています。またGT-RのみならずGTモデルもFRのためドリ車として活躍しており、このおかげでセダンの魅力も引き出されました。このように安定感や安心感も特徴で、高性能でありながら扱いやすいグランドツーリングカーとしての魅力も備えています。
GT-R 35型

R35型GT-Rは2007年に登場し、日産のフラッグシップスポーツカーとして位置づけられています。3.8リッターV6ツインターボエンジンを搭載し、世界にも通じるスーパーカーへと登り詰めました。カタログ馬力は485馬力、実馬力では500馬力とされています。スカイラインGT-Rから決別した存在として大きなプレッシャーもあったと思いますが、見事その期待に応えた車でしょう。プレミアム・ミッドシップパッケージの採用や、空力性能の向上などにより、卓越した走行性能を実現しています。また、冷却性能の向上や、グリル&バンパー開口部の拡大など、細部にわたる改良が施されています。その後、度重なるモデルチェンジが繰り返されましたが、惜しくも2025年に生産終了が決定しました。ニスモやT-スペックなど様々なモデルが展開されましたが、18年の歴史に幕を閉じました。日産は現在、水野和敏氏の退任をきかっけにスポーツカーの未来が危ぶまれていますが、今後の活躍にも期待したいです。
フェアレディZ 32型
Z32型フェアレディZは1990年代初頭に登場し、3リッターV6ツインターボエンジン「VG30DETT」を搭載しています。カタログ馬力は280PSですが、実馬力では300馬力とされています。この車が280馬力規制のきっかけとなったとされ、今後の車業界に影響を与えました。車体に関しては2シーターと2by2の2種設定があり、寸法も微妙に異なっています。明確な違いとしては給油口の位置が異なっていることであり、マニアでないと気づかないと思います。欧州のスーパーカーのようなデザイン性や先進的な装備が当時のスポーツカーとして高い評価を受けました。
フェアレディZ 33型
Z33型フェアレディZは2002年に登場し、ロングノーズ・ショートデッキのスタイリングが特徴です。エンジンは3.5リッターV6「VQ35DE」を搭載し、カタログ馬力は280馬力になります。実馬力では230~240馬力とされ、FRの3.5リッターNA車として貴重な存在です。水野和敏氏と高橋孝治氏が隠れて新型スポーツカーの開発を進めていたのが始まりであり、社内政治が厳しい環境でZを作り上げたのは大きな功績と言えるでしょう。販売当時、日産はGT-R不在だったためフェアレディZが希望となっていました。そのためかマイナーチェンジを繰り返し、最終的には300馬力超えのモデルへと変貌しました。使用されたFR-Lプラットフォームは画期的であり、日産は一時的に経営難から脱却することができました。
フェアレディZ RZ34型
RZ34型フェアレディZは最新モデルとして登場し、3リッターV6ツインターボエンジン「VR30DDTT」を搭載しています。最高出力は405馬力で、スカイライン400Rと同様のエンジンを採用しています。実馬力では400~415馬力とされており先代よりもエンジンは小さくなりましたが、パワーアップしました。見た目が変わっただけなどのコメントを見ますが間違いなく中身も見直されており、スポーツカーの人気が低迷している時代にこのような新型車を登場させたのは驚きです。また高額ながらニスモ仕様も登場しており、Zに対する意欲的な姿勢が感じられます。
180SX
180SXは1989年から1998年まで生産されたFRハッチバッククーペです。リトラクタブルヘッドランプや、スラントノーズ、大型バンパーなど当時のスポーティーなデザインが特徴です。カタログ馬力は205馬力ですが、実馬力では140~170馬力程度とされています。しかし、この車の魅力はドリフトとして長けていることやカスタムやチューニングの幅が大きいことでしょう。S13型シルビアとは兄弟車になりますがS14型シルビアが登場しても180SXの生産は継続されていたので、FRスポーツカーとして地位を築いたのは確かでしょう。ボディーラインは無駄がなくシンプルで流れるような形状で、リアフェンダーからリアエンドにかけての「ラップラウンドテール」も特徴的です。
シルビアS15型
S15型シルビアは1999年に登場し、スペックSは2.0リッター直列4気筒NAエンジン「SR20DE」を搭載しています。カタログ馬力は165馬力で、実馬力では130~160馬力とされています。この車もドリ車として定番であり、いかにもスポーツカーらしい見た目が印象的です。また、電動ハードトップを搭載したオープンモデル「ヴァリエッタ」も存在し、爽快なドライブを楽しむことができます。5ナンバーサイズでありながら後部座席も用意されており、実用性にも優れています。なお、ターボ仕様のスペックRではカタログ馬力は250馬力となっています。
まとめ
日産のスポーツカーは、各モデルが独自の特徴と魅力を持ち、多くのファンを魅了してきました。スカイラインGT-Rシリーズの卓越した性能や、フェアレディZシリーズのデザイン性、180SXやシルビアのスポーティーな走りなど、それぞれが日産の技術力と情熱を体現しています。今後も、日産のスポーツカーがどのような進化を遂げるのか、非常に楽しみです。
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説