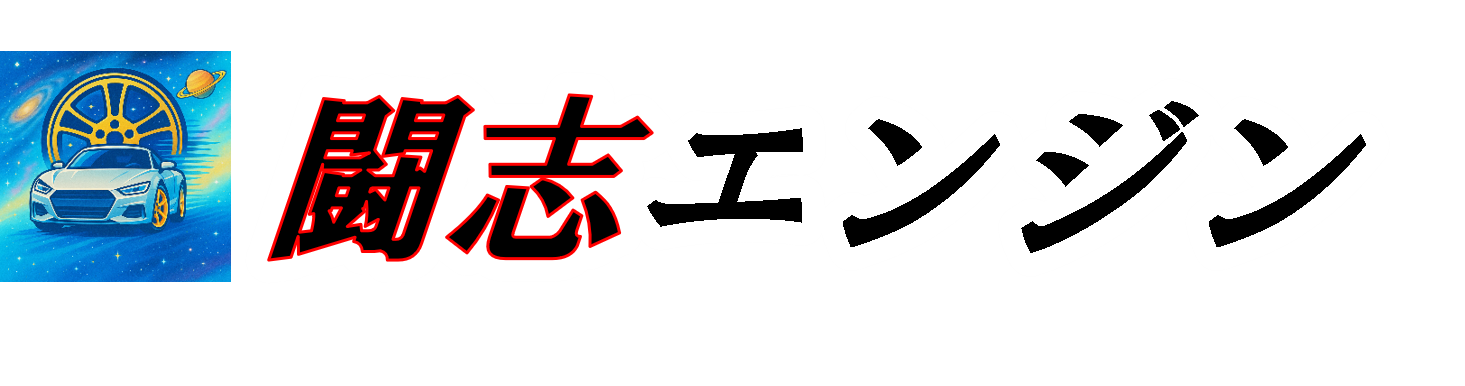ホンダ・S660の実馬力は何馬力?シャシダイ計測と体感のギャップを徹底解説

本記事は広告を含みます。
ホンダ・S660の「実馬力」は、カタログに記された64PSと同義ではありません。本記事では、シャシダイ方式や補正規格の違い、季節・燃料が与える影響、MT/CVT差や年式差までを、初心者でも実践できる手順と例えで解説しました。正しく測り、条件を揃えて比べることで、数字と体感のズレが小さくなります。
ホンダ・S660の実馬力は何馬力?シャシダイ計測と体感のギャップを徹底解説

S660の「実馬力」を語るとき、まず前提として“何の馬力を指すのか”を揃える必要があります。カタログに記載されるS660の最高出力は47kW[64PS]/6000rpm、最大トルクは104N・m/2600rpmで、これはエンジン単体を標準環境に補正して測るネット出力です。実際に多くのユーザーがショップで計測するのは、車両状態のままタイヤやハブを介して得る「ホイール(またはハブ)出力」で、駆動系損失を含むため値は小さくなりやすいのです。まずはエンジン出力(カタログ)とホイール出力(計測)の“ものさしの違い”を理解しておくと、数字の解釈がぐっと楽になります。公式諸元はHondaのアーカイブに残っており、規格化された測定方法はSAE J1349などに定義されています。(ホンダ, SAE International)
実馬力とは何か:カタログ値・エンジン出力・ホイール馬力の違い

エンジン出力は、補機を装着した状態でベンチ上のエンジンに負荷を与え、温度・湿度・気圧を所定の式で補正して“比較できる値”に整えたものです。日本(JIS)や欧州(DIN)、米国(SAE)には似た思想の規格があり、今日の乗用車カタログはほぼネット出力で統一されています。一方の実馬力は、タイヤやハブを介して車両全体の損失を含んだ出力を示し、路面とタイヤの相互作用、油温やギヤ油の粘度、ベアリング抵抗など現実の要素が入り込みます。つまり「カタログ64PSなのに、計ったらそれ以下だった」は異常ではなく、ものさしの場所が違うから当然、という理解が正しいのです。規格や補正の背景はSAE J1349の解説や、DIN(かつてのDIN 70020)の説明を参照すると把握しやすいです。(SAE International, ウィキペディア, Ate Up With Motor)
シャシダイの種類と特性:ローラー式/ハブ式/慣性式・電磁式

計測機の方式差も、出力値の“傾き”を生みます。ローラー式はタイヤをドラムに押し当てて測るため実走に近い反面、空気圧・タイヤ温度・ストラップ固定力などで微妙に値が動きます。ハブ式(Dynapackなど)はホイールを外してハブに直接接続し、タイヤの不確定要素を排するため再現性に優れます。負荷の与え方も二種類があり、ローラーの慣性で負荷を作る「慣性式」と、エディカレント(電磁)ブレーキで任意の負荷を作る「電磁式」があります。ターボ車の燃料・点火・過給学習を丁寧に追うには、一定負荷を保持できる電磁式(DynojetのエディカレントブレーキやDynapackの油圧負荷)が有利です。方式ごとの長所短所を踏まえ、同一機材・同一補正で前後比較を積み上げるのが実務的な“速さに効く”使い方です。(dynapackusa.com, dynojet.com, dynapack.com)
体感とのズレが生まれる理由:ギア比・トルク曲線・レスポンス
グラフ上のピーク出力が同等でも、走りの軽快さが異なるのは珍しくありません。S660は車重がおおむね830〜850kgでミッドシップ(MR)という骨格を持ち、小排気量ターボながら回転系の慣性が小さいため、スロットル操作に対するエンジン回転の立ち上がりが鋭い個性があります。結果として、ピーク値だけでは語れない“中域の厚み”と“つながり”が体感加速を左右します。CVTは測定上のホイール値がやや低く出ても、常に有利な回転に張り付ける制御で一般道の追い越しが俊敏に感じられる場面があり、グラフの一数字と体感が食い違う典型例になります。諸元(重量・変速機・最終減速比など)はHondaの主要諸元PDFにまとまっており、計測値を読む際はこれらの前提も併せて確認しておくと、数字と実走の橋渡しがしやすくなります。(ホンダ)
計測時の注意点:タイヤ空気圧・固定方法・補正係数
実馬力を“比べる道具”にするには、再現性の高いプロトコルづくりが重要です。
- 最低限のチェックリストを示します。
- 使用ギア、タイヤ空気圧、ストラップの固定位置とテンション、送風機の風量と角度を固定します。
- 吸気温(IAT)・外気温・気圧・湿度を記録し、同じ補正式(例:SAE J1349)で補正した値で比較します。
- 連続計測ではタイヤやATFが過熱して値が落ちやすいため、インターバルを設けて中位値を採用します。
エディカレント方式では一定負荷の定常試験やステップ負荷が可能で、ターボ車の学習挙動や点火時期の変化を丁寧に追えます。Dynojetのエディブレーキ資料やSAEの解説は、補正と負荷制御の考え方を掴む際の一次情報として有用です。(dynojet.com, SAE International)
(参考元:Honda「S660」主要諸元PDF/アーカイブ、SAE J1349解説ページ、Dynapack技術インフォ、Dynojetエディカレントブレーキ資料。(ホンダ, SAE International, dynapackusa.com, dynojet.com))
ホンダ・S660の実馬力を検証:ノーマル/マフラー/ECU別に比較

S660の実馬力は「どう変えたか」より「どう測ったか」で見え方が大きく変わります。ここではノーマルを基準に、吸排気とECU変更の“現実的な変化”を、初心者の方にも伝わるように整理します。体温計で例えるとわかりやすいのですが、体温そのもの(=エンジンの潜在能力)と、測り方(口内/耳/脇:=ダイナモの方式)が違えば表示も変わる、という関係に近いです。ノーマル基準を丁寧に作り、同じ測り方で前後比較を積み上げれば、小さな違いも意味を持つ“使えるデータ”になります。公式の主要諸元はHondaのアーカイブに公開され、測定の補正思想はSAE J1349などにまとめられています。計測方式の特性はDynapackやDynojetの技術資料が参考になります。(ホンダ, SAE International, dynapackusa.com, dynojet.com)
ノーマル(完全純正)状態のベースラインを作る

まずは“基準体温”づくりです。部品を変える前に、純正状態で複数回の計測を行い、その日の中位値をベースラインにします。初心者の方は、ここを丁寧にやるだけで後の判断が格段に楽になります。手順はシンプルです。
- 同じ燃料(同一銘柄・同一スタンド推奨)を満タンにし、タイヤ空気圧を規定値に合わせます。
- エンジン・駆動系を温め、送風機の位置と風量、ストラップ固定のテンション、使用ギアを“記録して固定”します。
- 3~5本連続ではタイヤやATFが過熱し数値が落ちやすいので、間隔を空けて計り、中位値を採用します。
やることは体調記録と同じで、「いつ・どこで・どう測ったか」を残すことが重要です。
吸排気(エアクリーナー/マフラー)変更時の実馬力変化
吸気と排気は呼吸。息の通り道を少し広げても“肺そのもの”は変わらないため、ピーク出力の変化は概して小さめです。一方で、中回転の“息継ぎ感”が薄れたり、レスポンスが軽く感じられるなど、体感面の改善は出やすい領域です。初心者が陥りがちなのは、音量や音質の変化を“速さ”と混同することです。たとえばマフラーを替えた直後に「速くなった気がする」と感じても、グラフでは中域のトルクが少し滑らかになっただけ、ということは珍しくありません。だからこそ、ノーマルの曲線と重ねて“面積”(トルクの積分的な量)を見比べるのが有効です。ローラー式ではタイヤの変形が影響しやすく、連続計測で数値が下がることもあるため、必ずインターバルを設けます。測定方式や固定条件の違いで値が振れやすい点は、DynojetやDynapackの資料でも言及されています。(dynojet.com, dynapackusa.com)
ECUチューニング別の出力特性:点火・過給・燃調の影響
ECUは“呼吸と点火の司令塔”です。点火時期を適正化し、過給圧の立ち上がりや燃料噴射を整えると、ピーク値よりも“曲線の形”が変わります。特に街乗り~ワインディングで効くのは、3000~6000rpmの中域を太らせるセッティングで、カタログの64PSという上限の中でも「押し出し感」がはっきり変わります。初心者向けの目安としては、夏の高い吸気温(IAT)ではノックマージンが減るため学習で点火が遅角し、ECUを変えても期待ほど伸びないことがあります。逆に涼しい夜や冬は“同じ設定”でも体感が良くなりやすい。これは規格化された補正(SAE J1349)で想定されている現象そのもので、比較するときは当日のIATや気圧も併記しておくと納得感が高まります。負荷一定で学習挙動を観察できるエディカレント式のベンチは、ターボ車の再現性確保に有効です。(SAE International, dynojet.com)
CVTとMTでの計測条件差と比較のコツ
CVTは“無段”という特性上、ギア固定が難しく、そのままスイープすると回転と負荷が落ち着かずバラつきやすいです。初心者の方は、ショップで「どのレンジで回転を固定するのか」「トルクコンバータ領域を避けられるか」を必ず確認してください。測り方のコツは、①油温管理(ATF温度が上がると滑り傾向が強まり数値が落ちやすい)、②一定負荷の確保(エディカレント式なら保持がしやすい)、③同一日の同一補正でMTと比較、の三点です。なお、MTは物理損失が相対的に小さいため同条件ならホイール出力がやや高く出る傾向がありますが、CVTは実走で“常に美味しい回転”を使えるため、中間加速の体感では拮抗する場面もあります。方式ごとの持ち味と測定の流儀を理解して比較すれば、「グラフの数字は低いのに走る」という疑問も解けます。計測方式の違いによる再現性の話はDynapackの技術イントロでも触れられています。(dynapackusa.com)
(参考元:Honda「S660」主要諸元/アーカイブ、SAE J1349 認証パワー解説、Dynapack technical intro、Dynojet Eddy Current Brake ガイド。(ホンダ, SAE International, dynapackusa.com, dynojet.com))
ホンダ・S660の実馬力の真実:カタログ64psとの違いと測定方法

カタログに載る「64PS」は、S660のエンジン単体を規定状態に補正して測った“ネット出力”です。Hondaの公式アーカイブでは、最高出力47kW[64PS]/6000rpm、最大トルク104N・m/2600rpmと明記されており、これはあくまでエンジンの能力を同一条件で比較するための指標になります。一方、私たちがショップのダイナモで得る「実馬力(ホイール/ハブ出力)」は、ミッションやデフ、軸受、タイヤなど車両側の損失を含むため、同じS660でも数字が小さく出るのが普通です。まずは「測る場所(エンジン/車両)と補正」が違えば値も変わる、という前提を押さえてください。初心者向けのたとえで言えば、体温計の“舌下と脇”で表示が違うのと同じ関係です。(ホンダ)
軽自動車の出力表記と自主規制の基本
日本の軽自動車は出力上限が64PSという“枠”の中で設計されています。ここで言うPSはドイツDIN由来のメトリック馬力で、1PS≒0.986hpという換算関係があります。DIN規格(DIN 70020)は、エンジンを実装状態に近い条件で測る思想を採り、今日のSAE J1349(ネット)と近い立ち位置です。つまり、カタログ64PSは“エンジンとしての比較値”であり、路面に伝わる力そのものではありません。この違いを知らないと「測ったら60PSも出ていない=おかしい」と誤解しがちですが、ホイール側での損失(駆動系・タイヤ)を通る以上、数値が落ちるのは自然な結果です。初心者の方は、まず「PSの正体」と「ネット出力=比較用の規格値」という2点をセットで理解しておくと、実測値の読み解きがぐっと楽になります。(ウィキペディア, Ate Up With Motor)
計測規格(SAE/DIN/JIS)と補正の考え方
同じエンジンでも、外気温・気圧・湿度が違えば吸入空気の密度が変わり、出力は上下します。そこで各規格は「標準大気」に補正する考え方を用意しています。SAE J1349は、顧客が使う現実の条件を正しく反映しつつ再現性の高い比較を可能にすることを目的に定められた標準で、メーカーが“認証パワー”として用いる手続きを整えています。要するに、別の日・別の場所で測っても同じ物差しで比べられるようにするための“温湿度のものさし”です。実走でも夏の高温・低気圧では加速が鈍く、冬の低温・高気圧では元気に感じるのと同じ理屈で、学術的な検証でも気温・気圧の変化がエンジン出力に与える影響が確認されています。実馬力を比較するときは、補正方式(SAE/DIN等)を統一し、当日の外気条件と吸気温(IAT)を記録しておくと、数字の“理由”が説明できるようになります。(SAE International, SciELO Brasil)
ダイナパック vs ローラーダイナモ:データの読み比べ
実馬力の“見え方”には、計測機の方式差も効いてきます。ローラー式はタイヤをドラムに押し当てて測るため、路面とタイヤの相互作用を含めた“実走に近い”条件で出力を拾えますが、空気圧や温度、固定テンション、ローラー表面の状態などで微小な滑りや発熱が起こり、値が揺れやすい面があります。対してハブ直結のDynapackはホイールを外してハブに直接接続する構造で、タイヤ由来の不確定要素を排し、同条件比較の再現性に優れます。その一方、タイヤ損失を通らない分、同じ車両でも“やや高め”に出る傾向があり、方式をまたいだ絶対値の横並びは慎重に行うべきです。さらに、Dynojetなどエディカレント(電磁)ブレーキ付きの機材では一定負荷の保持や段階負荷が可能で、ターボ車の学習挙動や点火時期の変化を丁寧に追えます。初心者の方は、まず「同じ機材・同じ補正・同じ固定条件」でノーマル→変更後を積み上げ、曲線の“形(面積)”と再現性を重視して読み比べる、という基本を守るだけで評価の精度が大きく上がります。(dynapack.com, dynapackusa.com, dynojet.com)
ホンダ・S660の実馬力は季節や燃料で変わる?夏・冬・ハイオク別の理由

実馬力は“同じクルマでも日によって違う”と感じやすい領域です。背景にあるのは吸気密度とノックマージン、そしてECUの学習制御です。夏は吸気温が上がって空気密度が下がり、同じ過給圧でも実際にシリンダーへ入る酸素量が減ります。さらにノックのリスクが高まるため、ECUは点火時期を遅角して保護に回り、結果としてホイール出力が落ちやすくなります。逆に冬は空気密度が上がり過給効率も良くなるため、体感的に元気になりますが、油温やタイヤ温度が低いことによる損失増やトラクション不足という別の壁が現れます。燃料はオクタン価の高いハイオクのほうがノック耐性に余裕があり、学習が進んだ個体では点火が進角側に寄って“ブレの少ない速さ”につながることがあります。ただし取扱書に指定された燃料を前提に設計されていますので、燃料の選択はまずメーカー指定に従うことが大切です。以下では初心者の方にも分かりやすい例を交え、季節・燃料で何が起きるかを整理します(測定の考え方自体はSAE J1349などの補正思想に沿うと理解しやすいです)。
吸気温・気圧・湿度がターボ出力に与える影響
吸気温は“酸素の濃さ”を左右します。理科の授業で習う気体の法則に照らせば、温度(絶対温度)が上がるほど密度は下がります。たとえば吸気温が20℃(約293K)から60℃(約333K)に上がると、理想気体として単純化した場合の密度は約293/333≒0.88、ざっくり12%前後低下します。ターボは過給圧で空気量を稼げますが、インタークーラー出口の温度が高いと同じブーストでも酸素の“実効量”は目減りします。加えて湿度が高い日は空気中の水蒸気分圧が増え、酸素の分率が下がるため、微妙に燃焼条件が不利になります。こうした条件が重なる真夏日の渋滞後、信号で止まってから再加速すると「いつもより重い」と感じるのは典型例です。ECUは吸気温センサーとノックセンサーから得た情報をもとに点火時期を遅角してエンジンを守るため、ダイナモでも実馬力が下振れしやすくなります。一方、冬の乾いた冷気は密度が高く、同じアクセル開度でも“押し出し感”が強まりますが、冷間時は油の粘度が高く駆動損失が増えやすいことも覚えておきたいポイントです。
燃料オクタン価(レギュラー/ハイオク)とノック制御
オクタン価は“ノックしにくさ”の尺度です。S660のECUはノックセンサーで燃焼状態を見張り、ノック兆候があれば点火を遅らせて保護します。オクタン価の高いハイオクはノックに強いため、同条件下では点火がより進角方向に寄りやすく、再現性の高い出力が得られる場合があります。ここで誤解してほしくないのは、「ハイオク=必ず数馬力アップ」ではないことです。ECUのマップ設計や学習状況、吸気温などの環境条件が揃って初めて“違い”が現れます。初心者向けの身近な例でいえば、暑い昼間にレギュラーで軽いノックが出ていた個体が、夜の涼しい時間帯にハイオクへ切り替えたところ遅角量が減り、同じブーストでも中域の粘りが増した——といったケースです。測定で比較するなら、燃料を切り替えた後にECUの学習が落ち着くまで数十キロ走る、IATと外気条件を記録する、同一の補正でグラフを重ねる、といった手順を守ると差分が見えやすくなります。なお、燃料選択は必ず取扱書の指定に従い、公道では法令に適合した範囲で行うべきです。
夏のヒートソーク対策:インタークーラーと冷却
真夏は停車中に吸気系やターボ周りが熱を溜め込み(ヒートソーク)、再発進で一気にIATが跳ね上がります。これは上り坂や追い越しの“ここ一番”で効いてしまうため、対策の優先度は高いです。実践的には、走行風を効かせる導風と遮熱、そして冷却インターバルの取り方で差が出ます。
- 導風と遮熱:インタークーラーに確実に風が通るダクト取り回し、遮熱板や断熱テープでタービン周りの輻射熱を遮る。
- IATの監視:OBD計測器でIATを常に把握し、一定温度以上ではクールダウン走行を挟む運用にする。
- サーキット運用:連続周回の最後に1~2周のクーリングを義務づけ、ピットイン後はボンネット内に送風を当てる。
これらは派手な“パワーアップ”ではありませんが、夏場の実馬力の下振れを抑え、再現性を高めるうえで費用対効果の高い手当てです。初心者の方ほど、まずは“冷やす・測る・待つ”の三拍子を徹底することをおすすめします。
冬の過給応答とトラクションの注意点
冬はIATが下がって空気密度が上がるぶん、同じアクセル開度でもターボの“押し”が強まり、実馬力は上振れしやすくなります。ところが、路面温度とタイヤ温度が低いとグリップが立ち上がらず、ホイールスピンで駆動力が路面に伝わらないことがあります。ダイナモでは良い数字が出たのに、路上の0–60km/hが思ったほど伸びない——という矛盾はここから生まれます。また、油温・ミッションオイル・CVTフルードの粘度が高い冷間時は、内部損失が増えて回転の伸びに“重さ”が出ます。実走で速さに結びつけるには、暖機の丁寧さ、タイヤの適正空気圧とコンパウンド選び、MRらしい後輪荷重の積極的な活用(発進時は丁寧に荷重を後ろへ移す操作)など、基礎を欠かさないことが近道です。測定でも、冬場は“数値が良く出がち”という前提を置き、夏と同じ補正・同じ固定条件で比較し、必要なら実走ログ(加速度・区間タイム)も併用して判断すると、机上と現実のズレを小さくできます。
初心者でもわかる ホンダ・S660の実馬力:ホイール馬力とエンジン出力の読み解き方

実馬力を正しく読み解くコツは、「どこで測った数か」「グラフのどこを見るか」「実走にどう結び付けるか」の3点に集約されます。S660はカタログで64PSと示されますが、これはエンジン単体の“ネット出力”です。シャシダイで得られるホイール馬力は駆動系やタイヤの損失を含むため必ず小さくなります。たとえばノーマルのS660でホイール50PS前後が報告されやすいのは、64PSから損失を差し引いた“現実の路面へ伝わる力”を測っているからです。ただし損失は一定の%で決まるものではなく、油温・タイヤ銘柄・空気圧・ミッション形式(MT/CVT)などで揺れます。そこで、①同じ機材・同じ補正・同じ固定条件で比べる、②ピーク値だけでなく“曲線の形と面積”を見る、③実走ログと突き合わせる、という順序で理解していくと、数字が「速さの指標」として活きてきます。以下では初心者の方にも取り組みやすい手順と考え方を、具体例を交えて解説します。
ドライブトレイン損失の考え方:FF/MR・タイヤ・油温
損失とは、エンジンが生んだ力が駆動系やタイヤで熱に変わって失われる部分です。一般にMTの二輪駆動車で10~20%、CVT/ATでそれ以上という“目安”が語られますが、S660(MR・MT/CVT)でも状況により幅があります。たとえば、カタログ64PSの個体がハブ式やローラー式でホイール50PSだった場合、単純換算なら約22%の損失ですが、同じ個体でも油温が十分に上がってギヤ油の粘度が下がると1~2PS分“軽く”出ることがあります。タイヤも重要です。ハイグリップで扁平率の低いタイヤはローラー上で変形損失が増え、空気圧が低いほどローラーに押しつぶされて数値が落ちがちです。初心者の方は、計測のたびに「タイヤ銘柄・サイズ・空気圧」「油温・水温」「外気条件」をメモしておき、ベースラインの近傍条件で比較するクセを付けるだけで、データの信頼度がぐっと上がります。なお、CVTは構造上の滑りと熱の影響を受けやすく、ATF温度を管理しない連続計測では後半に数値が下がる“あるある”が起きます。測る前に温度を整え、1本ごとにインターバルを置く運用が有効です。
グラフの見方:パワーカーブとトルクカーブの基礎
ダイナモのグラフは「縦軸=出力またはトルク」「横軸=回転数」が基本です。パワーは“トルク×回転数”ですから、ピークだけを比べても走りの“使いやすさ”は分かりません。S660で日常的に使うのはおおむね3000~6000rpm帯で、この帯域のトルクが太く滑らかであるほど、合流や追い越しでの“押し出し感”が強くなります。初心者の方は、グラフを2枚重ねて「3000、4000、5000rpmの各点でどちらが高いか」「シフトアップ後の回転(例:6000→次ギアで4000付近)にトルクの“山”が残っているか」を見ると、数字が体感に結びつきます。もう一つの落とし穴が“スムージング”です。滑らかに見やすくする処理を強くかけると、ノック回避や補正動作で起きた細かな落ち込みが埋もれ、実走で感じた“息継ぎ”が見えなくなることがあります。比較時はスムージングの設定も揃えましょう。計測方式が違うグラフの絶対値を横並びにせず、同じ方式・同条件の曲線の“面積と形”で判断する——これが最短ルートです。
実馬力から実走の加速を予測する簡易モデル
実馬力を“走り”に翻訳するには、パワーウエイトレシオとギア比の二つを押さえます。S660(約830~850kg)でホイール50PSなら、パワーウエイトはおよそ16~17kg/PSというイメージです。ここから0–100km/hの“目安”を出す簡単な方法として、同クラス車の実測データに対してパワーウエイトの比を当てはめ、ギア段ごとの駆動力(トルク×総減速×タイヤ半径)で補正するやり方があります。たとえば、ノーマルMTの0–100km/hが約12~14秒のレンジにあると仮定し、中域トルクが厚くなるECU最適化でホイール+数PS、さらにギアの繋がりが良くなると、カタログ上の“64PSの壁”を超えずとも実走の区間タイムが目に見えて短縮されます。実験としては、スマホの加速度計アプリやGPSロガー、OBDリーダーで「2速40→80km/h」など固定区間を繰り返し計測し、温度や風向きが似た日で比較すると、グラフの“面積アップ”が秒単位の差に転化することを体感できます。ここでも重要なのは、同じ道路・同じ向き・同じ荷物・同じタイヤ圧という“再現性の作法”です。
よくある誤解とデータの落とし穴
実馬力の世界は思い込みの罠が多いです。典型は、異なるダイナモ(ローラー/ハブ、慣性/電磁)や補正方式(SAE/DIN)が混在した数字を横並びにして優劣を断じるケースです。方式が違えば“測る場所”と“負荷のかけ方”が違い、絶対値がズレるのは自然です。もう一つは、音や振動の“プラシーボ”です。吸排気の音量が増した直後は速く感じがちですが、グラフを重ねるとピークは不変で中域のうねりが少し滑らかになっただけ、ということも珍しくありません。また、連続計測でタイヤやATFが過熱して後半の数字が下がるのに、最初と最後を比較して「パーツAは遅い」と結論づけるのも誤りです。初心者の方は、①同一機材・同一補正・同一固定、②中位値を採用、③IAT・気圧・油温を記録、という3点を守るだけで、データの信頼区間を“狭く”できます。最後に、グラフは“目的を達成するための道具”であり、街乗り重視なら中域トルクの面積、サーキットなら連続負荷での熱安定性と再現性、と評価軸を使い分けることが、S660という軽量ミッドシップを最も気持ちよく、そして速く走らせる近道になります。
チューニングでどこまで伸ばせる?ホンダ・S660の実馬力と安全なパワーアップ指針

S660の実馬力を底上げするうえで最も重要なのは、「どの順番で」「どこまで」を決め、再現性と耐久性を両立させることです。軽量なミッドシップという素性は“少しの最適化が体感に直結する”一方で、熱と燃料・点火の余力を超えると数値は出ても持続しない、という現実もあります。初心者の方は、いきなりピーク値を追うのではなく、ベースラインを作り、冷却とログ環境を整えてから吸排気→ECU→必要に応じて燃料系・過給系の順に段階を踏むと、投資対効果が高く失敗が少ないです。実走で“曲線の面積(中域トルク)”が増えるセッティングは、ピーク一点の誇張より確実に速さへつながります。公道では保安基準や車検適合が大前提で、OBD自己診断の監視項目を殺さないこと、触媒やO2センサー位置に配慮することは欠かせません(参考:Honda S660 取扱説明書・主要諸元、国交省 保安基準の概要、SAE J1349の補正思想、Dynapack/Dynojetの技術資料)。
吸排気・ECU・ブースト制御の優先順位
最初の一歩は“測るための環境づくり”です。IAT(吸気温)、ブースト、点火時期、ノック補正、空燃比のログを取れる体制を整え、ノーマルのベースラインを確定します。そのうえで吸排気を“通りよく、熱を持たせない”方向に整え、次にECUで点火・燃調・ブースト制御を最適化します。過給圧は上げれば数字が出ますが、IATの上昇とノックマージンの低下が同時に進むため、結果として“夏に走らない仕様”になりがちです。一定負荷での学習挙動を追えるベンチ(エディカレント式など)で、3000〜6000rpmの厚みを増やすことを意識すると、街中やワインディングでの押し出しが明確に変わります。
・優先順位の例:①計測とログ→②吸排気と遮熱→③ECU最適化→④必要に応じて燃料系→⑤過給系(段階的に)
ターボ・燃料系・点火系のボトルネック
S660のノーマルターボは街乗り応答に優れますが、高回転での排気背圧やコンプレッサ効率の限界に早く当たりやすい特性があります。ECUで中域の点火と燃調を整えるだけでも“体感の太さ”は変わりますが、さらに上を狙うと燃料ポンプ・インジェクタのデューティ、点火コイルのエネルギー、プラグの熱価といった周辺の余力がボトルネックとして現れます。排気温や排圧(EGBP)を監視できると、どこで“頭打ち”が来ているかが可視化でき、闇雲な過給アップを避けられます。点火側は失火やノックのマージンが削れると一気にパワーが落ち込むため、プラグの状態管理とコイル電源の健全化にも目を配ります。燃料は指定基準を守りつつ、継続的に噴射率が高止まりするなら上流(ポンプ)や配管の見直しも検討します。
信頼性と法規(車検・保安基準)を両立するポイント
日本の保安基準では、排ガス適合、騒音、灯火、OBD自己診断の観点からの適合性が求められます。触媒の位置や容積を変える改造はOBDモニタの合否や排ガス適合に直結し、エラー回避のための“モニタ無効化”は検査不適合のリスクを高めます。吸排気は「性能向上」と「適合」の折り合いが鍵で、車検対応品の選定、取付後の排気漏れ確認、チェックランプ有無の点検を徹底します。ECUはサーキット専用マップと公道用マップを分け、ノック検知やフェイルセーフを残すことが長期の安心につながります。最終的に速さと安心を両立している仕様は、データの再現性が高く、夏冬での“ブレ”が小さいという共通点があります。法令の詳細は国土交通省の公開資料や検査事務規程の範囲を確認し、グレーゾーンに踏み込まない判断が賢明です。
冷却・潤滑・クラッチ/CVT保護のアップグレード
熱はターボ車の天敵です。IATの抑制、油温・水温の安定化、そして駆動系の保護は、どのチューニング段階でも“先回り投資”する価値があります。インタークーラーの容量アップや導風ダクトの最適化、タービン周りの遮熱、オイルクーラーの適切なサーモ制御は、同じブーストでも学習遅角を防ぎ実馬力の再現性を押し上げます。MTはクラッチ容量とペダルフィールのバランス、CVTはATFの熱対策とトルク制限ロジックへの配慮が要点です。中低速トルクを盛りすぎるとCVT保護制御が介入し、実走がかえって鈍ることもあります。
- 効果が出やすい“先行投資”例:導風+遮熱、IAT監視、油温監視(OBDや追加メーター)、クーリング手順の徹底
- 駆動系の保護例:MTはクラッチ一式の適正化、CVTはATFクーラー・油温管理、連続高負荷時の休止インターバル
年式・MT/CVTで違いはある?ホンダ・S660の実馬力を徹底比較

S660は登場から生産終盤にかけて細かな年次改良や特別仕様の追加がありましたが、実馬力に決定的な“飛び級”が起きるような大変更は限定的です。とはいえ、ECUの細部ロジックや排気浄化のチューニング、装備差による重量やタイヤの違いは、シャシダイの曲線や実走の加速感にじわりと影響します。さらに、ミッション形式の違いは計測方法そのものに関わるため、MTとCVTを横並びに語ると誤解が生じやすい領域です。本章では、初心者の方にも混乱が少ないように「年式差の読み方」と「MT/CVT比較の勘所」を具体例とチェックリストで整理します。参考情報としては、Hondaの主要諸元や取扱説明書、各計測機メーカー(Dynapack/Dynojetなど)の公開資料が基本になりますが、以下はそれらの一般知見に基づく“実務的な読み方”です。
年式ごとの小変更とECUロム差の可能性
年式差でまず影響が出やすいのは、ECUの細かなキャリブレーション、触媒やO2センサー制御の最適化、装備変更に伴う車重やタイヤの変化です。たとえば同じノーマルでも、早期型と後期型(または特別仕様)で吸排気の共振点や遮熱の取り回しが微妙に異なれば、中域のトルクの“盛り上がり方”や立ち上がりの滑らかさに差が出ることがあります。ただし、それは「ピークが別物になる」というより、3000〜6000rpm帯の曲線形状がわずかに整う、あるいはノック制御の介入タイミングが変わって体感の“荒さ”が薄れるといった質的変化として現れやすいです。特別仕様(例:足回りや補強、空力が異なるグレード)は、パワートレーンが同一でもローラー式計測での再現性に影響することがあります。サスペンションの減衰やボディ補強により接地が安定すると、タイヤの微小スリップが抑えられ、同じ実馬力でもグラフが“きれい”に出ることがあるからです。初心者の方が年式差を検証する際は、ECUロムのバージョンや排気系の品番、車重・タイヤサイズと銘柄を計測データと一緒に記録すると、後日比較の説得力が高まります。
年式差を読むためのチェックポイント(例)
- 同一機材・同一補正・同一固定条件で“同日比較”を優先する
- ECUロムのバージョン、触媒やO2センサー位置/品番の記録を残す
- 装備差(シート・ホイール・タイヤ)による車重/慣性の差を併記する
MTとCVTの最終減速比・損失差の読み
MTとCVTは、実馬力の“見え方”と実走の“速さの出方”が噛み合いにくい代表例です。MTは機械損失が比較的小さく、シャシダイでもホイール馬力が出やすい一方、ギア比は段階的なのでシフトアップ後に回転が落ち、トルクの“山”を外すと区間タイムが伸びません。CVTはドライブライン損失が相対的に大きく、計測数値はMTより低く出がちですが、実走では“常に美味しい回転”に張り付ける制御で中間加速が強く感じられる場面があります。最終減速比や実測タイヤ外径の違いも、同じ“50PS”でも速度レンジでの伸びを変化させます。計測時の勘所は次の三つです。第一に、MTは“どのギアで測るか”を固定し、シフトタイミングの影響を排除します。第二に、CVTは無段変速ゆえにスイープ計測が流れてしまうため、電磁ブレーキ付きベンチで一定回転・一定負荷を保持する、あるいは指定レンジで回転を固定するなど、手順をショップとすり合わせます。第三に、ATF温度の管理です。CVTは熱で滑り傾向が強まり、連続計測の後半に数値が“下り坂”になるのはよくある現象です。
MT/CVTを公平に比べる簡易プロトコル(例)
- MT:同一ギア・同一回転範囲で複数本。中位値を採用
- CVT:油温を管理し、一定負荷保持(エディカレント方式等)で定点比較
- 共通:IAT・外気条件・タイヤ銘柄/空気圧・スムージング設定を固定
実走評価と結びつけるコツ(例)
- 同一路線・同方向・一定荷重で「40→80km/h(2速相当)」など固定区間を計測
- ダイナモの“曲線の面積(中域トルク)”が大きい仕様ほど、上記区間の時間短縮が安定して再現されやすい
- グラフのピーク値だけで判断せず、シフト後の回転域にトルクの山が残るかを確認
総じて言えるのは、年式差もミッション差も“絶対値の一点”ではなく、“条件を揃えたときの曲線の形と再現性”として読むべきだということです。初心者の方は、データを「測り方の履歴」とセットで残すだけで、ノーマル/軽度チューン/仕様違いの比較がいっそうクリアになります。
最後に

結論として、S660の速さはピーク出力の一点ではなく、中域トルクの面積と温度管理、そして再現性の高いプロトコルに支えられます。ノーマル基準を丁寧に作り、同一機材・同一補正で前後比較しながら、吸排気とECU、冷却を段階的に整えれば、季節に左右されにくい“走りの安定感”が得られます。
要点
- 実馬力は「エンジン単体の64PS(カタログ値)」と同じではありません。測定方式(ローラー/ハブ)や補正規格(SAE J1349 など)、当日の気象条件で値が動くため、同一機材・同一補正・同一条件での前後比較が本質です。 (SAE International, dynapackusa.com)
- 速さの体感はピーク値より「中域のトルク面積」と再現性で決まります。季節(吸気温・気圧・湿度)や燃料オクタン価は出力と点火時期に影響し、グラフの読み方にも直結します。 (SciELO Brasil, SAE International)
- チューニングは「測る→冷やす→最適化」を段階的に。吸排気・ECU・冷却の順で整え、法規(OBD/排ガス・騒音)への適合も意識すると、速さと安心を両立できます。 (dynojet.com, 国土交通省)
参考文献
- Honda「S660(2022年3月終了モデル)主要装備・主要諸元」
https://www.honda.co.jp/auto-archive/s660/2022/ (Honda) - Honda「S660 主要諸元(PDF)」
https://www.honda.co.jp/auto-archive/s660/2018/common/pdf/s660_spec_list_201804.pdf (Honda) - SAE International「About SAE J1349® Certified Power」
https://www.sae.org/standards/development/about-saej1349-certified-power/ (SAE International) - SAE International「Certified Power(SAE J1349/J1995)」
https://www.sae.org/certifiedpower/ (SAE International) - Dynapack USA「Technical Introduction」
https://www.dynapackusa.com/tech%20intro.htm (dynapackusa.com) - Dynojet「224xLC Two Wheel Drive Dynamometer(Eddy Current Load Control)」
https://www.dynojet.com/2wd-automotive-chassis-dynamometer-with-eddy-current-model-224xlc (dynojet.com) - Dynojet「Eddy Current Brake Installation and User Guide(PDF)」
https://www.dynojet.com/amfile/file/download/file/222/category/160/224Brake.pdf (dynojet.com) - Soares, S.M.C. et al. “Comparison of Engine Power Correction Factors for Varying Atmospheric Conditions”(PDF)
https://www.scielo.br/j/jbsmse/a/PYvWVw3p3Zbt7syV5zXtSdN/?format=pdf (SciELO Brasil) - 国土交通省「OBD検査 関係法令・通達集(PDF)」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/OBDkensa-regulations_set.pdf (国土交通省)
(※上記は記事で触れた“測定規格・計測機・公式諸元・法規”の一次情報/公式資料を中心に掲載しています。)
☆あなたへのおススメ☆
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説