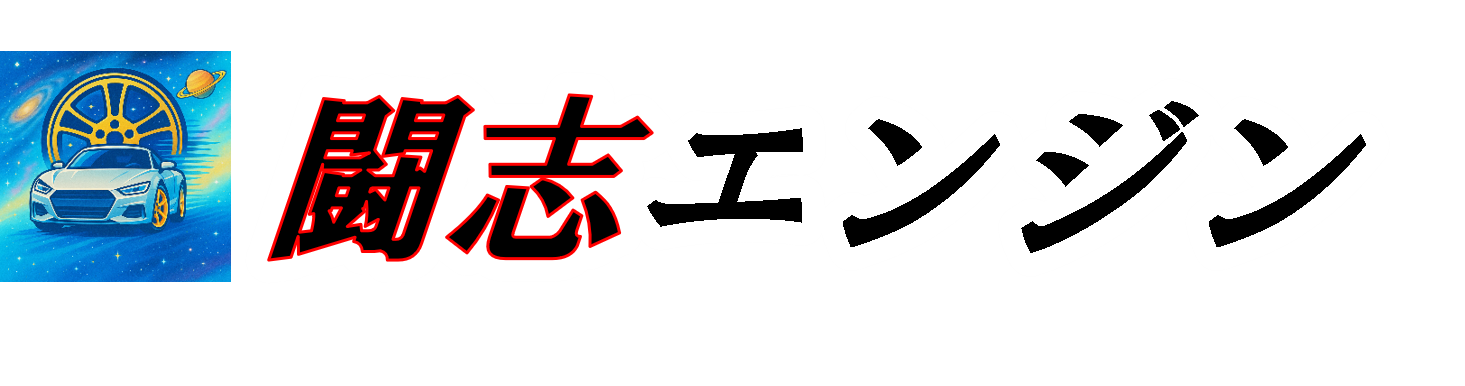幻になった国産スーパーカーたちの墓標

本記事は広告を含みます。
「スーパーカー」と聞くとフェラーリやランボルギーニなど海外メーカーの車を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、かつて日本の自動車メーカーでも夢のようなスーパーカーの開発が行われており、中には市販直前までこぎつけながらもお蔵入りとなってしまった“幻の国産スーパーカー”も存在します[1]。もし実際に販売されていたら…と思うと残念でなりません。この記事では、そんな 幻に終わった国産スーパーカー 達の代表例を振り返り、それぞれの挑戦と挫折、そして残された技術や教訓について考察してみます。
ホンダHSV-010の真実

ホンダHSV-010 GT(2010年)。初代NSX後継として開発されながら市販は叶わず、レース専用車としてデビューした幻のモデルです[2][3]。初参戦の2010年シーズンにSUPER GT GT500クラスでチャンピオンを獲得し、ホンダファンを熱狂させました。本田技研工業が開発していた「HSV-010」は、初代NSXの後継車種として Acuraブランドで2010年発売を予定された スーパースポーツカーでした[4]。2007年のデトロイトモーターショーで「Acura Advanced Sports Car Concept」としてコンセプトモデルが初披露され、北米市場を意識したエクステリアデザインとメカニズムを備えていました[5]。フロントに搭載されたエンジンは 3.5リッターV10自然吸気、駆動方式には高級セダン「レジェンド」で採用実績のある 電子制御四輪駆動システムSH-AWD を組み合わせ、まさにホンダが総力を結集した意欲作でした[2]。しかし2008年末の世界的経済危機(リーマンショック) により開発計画は白紙化され、市販化は断念されてしまいます[2]。

発売が幻に終わった後、ホンダはこのマシンをベースにレース専用車「HSV-010 GT」を開発しました。市販モデルが存在しない車ながらSUPER GT参戦が認められ、2010年にGT500クラスへデビューを果たします[6]。結果、デビューイヤーにシリーズチャンピオン獲得という快挙 を達成し、サーキットでその雄姿を見せてくれました[3]。皮肉にもレースの場でのみその走りを披露する形となりましたが、NSX後継の夢を一時的に託されたこのマシンは、多くのファンに強烈な印象を残しました。
F1技術を活かした挑戦

HSV-010開発には、ホンダの持つF1技術やノウハウも随所に活かされていたと言われます。V10エンジンは当時のレギュレーション下のF1を彷彿とさせる高回転型で、最高出力は約500馬力級に達する見込みでした[7]。また前輪駆動をベースに後輪にも駆動力を配分できるSH-AWDシステムは、四輪のトラクションを最大化する先進技術であり、高いコーナリング性能と安定性を両立する狙いがありました。これはまさに「公道に活かすF1テクノロジー」 と言える挑戦で、ホンダが培ったレーシングカー技術を市販スポーツカーに投入しようとした野心的な試みだったのです。

さらにシャシー開発にも最新の知見が投入され、ニュルブルクリンクでの走行テストも行われました[8]。空力性能の追求や軽量高剛性ボディの設計など、ホンダの技術の粋を集めて究極のロードゴーイングカーを作り上げようとした 点に、開発陣の本気度がうかがえます。残念ながら経済状況の悪化という外的要因で市販は実現しませんでしたが、もしHSV-010が市販されていればレクサスLFAなどと並ぶ和製スーパーカーの金字塔になっていたかもしれません。
なお、その後ホンダは仕切り直して新たなコンセプトのスーパーカー開発に着手し、2016年に2代目「NSX」 を発売することでNSXの系譜を復活させました[9]。HSV-010そのものは幻となりましたが、その スピリットや技術は次世代のホンダ車へ確実に受け継がれていった のです。
マツダRX500の未来志向デザイン

1970年東京モーターショーで公開されたマツダ「RX500」コンセプト。流線型のウェッジシェイプにシザーズドアやガルウィング式カウルを備え、当時としては驚異的な近未来デザインでした[10]。ロータリーエンジン搭載のこの実験車両は、開発が進み実走行も可能な状態でしたが市販化は叶いませんでした。マツダ「RX500」は1970年の第17回東京モーターショーに出展された 2ドアクーペ型コンセプトカー です[11]。マツダが社運をかけて推進していたロータリーエンジン技術をアピールする 近未来志向の実験車 として開発され、スポーツカー好きの注目を集めました。ボディは鋼管スペースフレームにFRPなど軽量素材の外板を組み合わせ、全長4.33mに対して全高わずか1.06mという低く構えたシルエット。ドアは 前ヒンジで上方向に開くシザーズドア、エンジンフード(リアカウル)は ガルウィング式 と、大胆なギミックを採用していました[10]。またリア部には走行状況に応じて色が変わるマルチカラーテールランプを装備し、加速時は緑、巡航時はアンバー(橙)、減速時は赤と発光色でドライバーの操作を周囲に伝える安全実験も行われました[12]。宇宙船を思わせるこれら数々の先進的アイデアは、まさに未来を先取りしたデザインと言えるでしょう。

内装・外装ともにショーカーとは思えない完成度で、「このまま市販化されてもおかしくない」と評されるほどでした[13]。事実、RX500はマツダにとっても 「コスモスポーツの後継となるロータリースポーツカーを本気で模索する研究モデル」 だったといいます[11]。空力特性を高めるための風洞実験まで行われており[14]、当時のマツダがいかに真剣にこの車の開発に取り組んでいたかがわかります。
ロータリーエンジンの限界に挑戦

RX500最大の特徴は、当時まだ実用化から日が浅い 2ローター式ロータリーエンジン をミッドシップに搭載していた点です。搭載されたのはコスモスポーツゆずりの10A型ロータリーエンジンですが、レース用チューンが施され最高出力 250ps を発生、車重850kgのボディを最高速度 250km/h まで到達させることが可能でした[15]。1970年当時にこの性能はまさにレーシングカー並みであり、マツダはロータリーのポテンシャルを極限まで引き出そうとしたのです。高速走行時の安定性確保のため前後重量配分は50:50と理想的に設計され、4速MTで後輪を駆動する駆動系も極めてオーソドックスながら洗練されていました[15]。

しかしながら、斬新すぎるパッケージングや当時の市場環境 を考えると量産・販売は現実的ではなく、結局RX500は市販に至りませんでした。ボディサイズこそ全幅1,720mm程度と現代基準ではコンパクトですが、低く幅広い車体にミッドシップロータリーという設計は、市販車としては異例づくめだったのです。その後のオイルショックもあり、マツダがスーパーカー市場に踏み出すことはありませんでした。とはいえ、RX500で得られた知見は無駄にならず、エンジンレイアウトの研究成果は後の1978年発売の初代「サバンナRX-7」へと受け継がれています[16]。RX-7ではエンジンこそフロントミッドシップ配置に改められましたが、50:50の重量配分思想などにRX500の影響を見て取ることができます。半世紀を経た現在、マツダは再びロータリースポーツの復活を模索しており、幻に終わったRX500の魂が新たな形で甦る日 をファンは期待していることでしょう。

なお、RX500は 世界に1台のみ製作 された車両ですが、幸運にも現存しています。初公開時はグリーン、その後イエロー、現在はシルバーに塗色が変更され、広島市の交通科学館に収蔵展示されている貴重な一台です[17][18]。幻の名車ではありますが、実物に会いに行ける点はファンにとって救いかもしれません。
日産MID4の革新的チャレンジ

日産「MID4-II」(1987年型)。日産が80年代に総力を挙げて開発したミッドシップ4WDスポーツカーMID4の進化版です。写真のプロトタイプは完成度が高く、市販直前までいきながらも最終的にお蔵入りとなりました。1980年代、日本の自動車メーカー各社がスポーツカー技術を競い合う中、「技術の日産」 として社運をかけた挑戦が「MID4」です。名前が示す通り「ミッドシップエンジン + 4WD」という革新的レイアウトのスポーツカーで、日産が持てる最新技術を結集して開発されました[19]。1985年のフランクフルトモーターショーで初披露された初代MID4(I型)は、3.0リッターV6 DOHCエンジン(VG30DE型・230ps)を車体中央に横置き搭載し、四輪操舵システムHICAS付きフルタイム4WDで全輪を駆動するという、当時としては画期的なコンセプトでした[20][21]。「ミッドシップは高いハンドリング性能、4WDは優れたトラクション」 と、それぞれF1マシンやラリーカーで実証済みの長所を組み合わせれば最強のスポーツカーになる──そんな発想のもと、生まれたのがMID4なのです[22]。

初代MID4はあくまで実験車・ショーモデルという位置付けでしたが、完成度の高さから「ぜひ市販を」という声が社内外から上がりました[23]。そこで日産は市販化を前提に改良を施した「MID4-II」 を2年後の1987年東京モーターショーに出展します[23]。MID4-IIではエンジンをより強力な 3.0リッターV6ツインターボ(VG30DETT・330ps) に変更し、レイアウトも縦置きに改められました[21][24]。スタイリングも初代より洗練された曲線基調となり、市販車さながらの内外装クオリティと相まって「発売秒読み」とまで噂される出来栄えでした[25]。
ミッドシップ・4WDという挑戦

MID4が挑んだ ミッドシップ・4WDの組み合わせ は、当時の市販車では未踏の領域でした。ミッドシップエンジン車としては国産初のトヨタMR2(1984年発売)があり、4WDスポーツとしてはマツダ・ファミリア4WDターボ(同1985年発売)などが存在しましたが、MID4はそれらを一台で実現し 「日本車でもフェラーリやポルシェに負けないスーパーカーを作る」 という夢を背負っていました[26][19]。開発責任者には名車スカイラインを手掛けた桜井眞一郎氏が起用され[27]、社内の意気込みも並々ならぬものがありました。

車両実験部では、市販化に向けて様々な課題に取り組んでいました。例えば、高出力ミッドシップ車特有の高速域での安定性確保や、4WD機構による重量増加とコスト増の問題です。日産はポルシェ959開発者のヘルムート・ボット氏に助言を求めるなど[28]、市販実現に向けた壁を乗り越えようと模索しました。しかし「真のスーパーカーを作るには相応の覚悟と投資が必要」 と指摘されたことや、バブル前夜の開発費高騰もあり、最終的には採算が取れないとの判断に至ります。莫大な開発費と工数 がネックとなり、MID4プロジェクトは断念せざるを得ませんでした[29]。

こうしてMID4-IIも発売直前でお蔵入りとなり、日産初の本格スーパーカー誕生の夢は潰えました。それでも、この挑戦は決して無駄ではありませんでした。二度の試作で培われたノウハウは日産の他モデルに活かされ、後述のように次世代車へ技術が受け継がれていきます。
技術は次世代車へと受け継がれた

MID4で開発・採用された 数多くの新技術 は、その後の市販スポーツモデルに脈々と受け継がれています[30]。例えばエンジンの VG30DETT型ツインターボユニット は、1989年発売の4代目「フェアレディZ (Z32型)」に搭載され市販化を果たしました。また四輪操舵システムの HICAS(ハイキャス) は当初R31型スカイラインで実用化され、さらに1989年登場の「スカイラインGT-R (R32型)」では発展型のスーパーHICASとして搭載されています[31]。すなわちMID4の先進メカニズムの多くはZ32型フェアレディZやR32型GT-Rへと流用され、形を変えて花開いた のです[32]。

デザイン面でも、MID4-IIで見せたロングノーズ・ショートデッキのシルエットやポップアップライト、ワイド&ローのスタイリングは、Z32やR32、同時期のS13シルビアなどに通じる要素が散見されます。MID4が目指した方向性は、90年代の国産スポーツカー群に少なからず影響を与えたと言えるでしょう。もしMID4が市販されていればNSXに先駆ける国産ミッドシップスーパーカーとなったはずですが、たとえ幻に終わってもその魂は次世代の日産車に受け継がれた のです。
ヤマハOX99-11の公道F1化マシン

ヤマハ「OX99-11」プロトタイプ(1992年)。F1用V12エンジンを積み、公道走行可能なフォーミュラカーを目指して作られた幻の一台です。タンデム2座のコクピットや戦闘機のようなドーム型キャノピーなど、その外観からして異彩を放っています。ヤマハ発動機が1990年代初頭に開発を計画した「OX99-11」は、まさに「公道で乗れるF1マシン」 をコンセプトとしたスーパーカーです[33]。ヤマハは1989年からF1にエンジン供給メーカーとして参戦しており、そのノウハウを活かして自社初の四輪市販車として本車を企画しました[33]。車名の「OX99」は、1991年にブラバム、1992年にジョーダンに供給した F1用3.5リッターV12エンジン (OX99型) に由来します[33]。このエンジンをベースに公道向けにデチューンしたとはいえ 最高出力450ps を発生し、車両重量わずか約1000kgの軽量ボディと相まって、その性能は桁外れでした[34]。レブリミット(最高回転数)は1万回転オーバーに設定され、12連スロットルやドライサンプ潤滑など 細部までF1直系の技術 が盛り込まれていたのです[35]。

OX99-11最大の特徴はそのユニークな車体レイアウトです。コクピットは丸みを帯びたドーム状のキャビンに タンデム2シーター(前後2人乗り) 配置を採用し、運転席は中央、助手席はその後ろに配置されています[36]。車体デザインはレーシングカーコンストラクターとして有名な 由良拓也氏 が手掛け、美しく流麗かつ機能美あふれるスタイルに仕上げられました[36]。フロントからリアにかけて絞り込まれた形状や大型のウイング状フェンダーは、空力を徹底的に追求した結果であり、「もし発売されていたらF1さながらのエアロダイナミクスを楽しめただろう」 と評される本格的ロードゴーイングカーでした[37]。エンジンスペックから見ても、その走行性能は当時の常識を超えています。非公式ながら 最高速度350km/h、0-100km/h加速3.2秒 といった驚異的な数値も伝えられており[35][38]、1990年代前半に計画されたスーパーカーとしては、英国のマクラーレンF1などと並び称される存在になり得たでしょう[39][40]。事実、一部では「日本版マクラーレンF1」と評されることもあります。
公道で乗れるフォーミュラカー

OX99-11が目指したのは、文字通りフォーミュラカーを公道で走らせることでした。ヤマハはオートバイやトヨタ2000GTの製作協力などで培った高回転エンジン技術を有し、それを究極の形で四輪車に応用しようとしたのです。当初、開発は英国のエンジニアリング会社と協力して進められ、シャシー製作もヨーロッパで行われました。1992年頃までに数台のプロトタイプが完成し、テスト走行も行われたとされます。車両価格は 約1億3000万円(当時)と見積もられ、1994年の発売を目指していました[41]。

しかし、プロジェクトは順風満帆とはいきませんでした。開発期間中にバブル経済は崩壊し、ヤマハ発動機の業績も悪化します。加えて、市販車メーカーではないヤマハが 販売網やサービス体制を整える難しさ もあり、この野心的計画は 世界的な経済変動の煽りを受けて断念 されてしまいました[41]。結局OX99-11は 3台の試作車が製作されたみに留まり、一般ユーザーが手にすることは叶わなかったのです[42][43]。幻となったとはいえ、OX99-11が自動車史に残したインパクトは計り知れません。モータースポーツファンや車好きを今なお惹きつけるカリスマ的存在であり、そのデザインモチーフやコンセプトは後のスーパースポーツにも影響を与えています。ヤマハは四輪市販車市場への参入こそ叶いませんでしたが、この挑戦で得た経験はエンジンサプライヤー事業などにフィードバックされました。例えば後年、トヨタのスーパースポーツ「レクサスLFA」のV10エンジン開発にヤマハが協力したことや、現在のヤマハ発動機が小規模生産のスポーツカー向けエンジン供給に強みを持つことにも、OX99-11で培われたノウハウが活きていると言えるでしょう。
最後に

幻の国産スーパーカーと呼ばれる車を振り返りました。共通しているのは「日本メーカーが真剣に世界水準のスーパーカー創りに挑んだ」という情熱と野心です。いずれも市販化には至りませんでしたが、技術は後の市販モデルに継承され、無駄にはなっていません。[32][30]振り返れば、これらの夢のようなモデルたちを現実にすることの難しさを痛感します[44]。高度な性能を実現するには莫大な資源が必要であり、経済情勢など様々な要因が立ちはだかりました。しかし、それら幻のスーパーカーが残したロマンは今も語り継がれ、後進のエンジニアやファンに刺激を与え続けています。
要点
参考文献
- 【41】 ベストカーWeb, “ホンダHSV-010、マツダRX500、日産MID4…幻になった国産スーパーカーたちの墓標”, 2024年4月5日 [1][10]
- 【11】 Wikipedia(日本語), “ホンダ・HSV-010” [7]
- 【25】 くるまのニュース, “発売直前でお蔵入りになったモデルもあり? 和製スーパーカー5選”, 2021年3月12日 [30][45]
- 【17】 マイナビニュース, “マツダが作った幻のスーパーカー? 「RX500」の実物に遭遇!”, 2024年2月22日 [46][16]
- 【31】 Wikipedia(英語), “Mazda RX-500” [12][18]
- 【19】 COBBY, “MID4が「幻のスーパーカー」と呼ばれる理由!なぜ日産は開発をやめた?”, (閲覧日:2025年8月)[22][28]
- 【26】 日産ヘリテージコレクション, “ニッサン MID4 (II型)” [32]
- 【3】 ベストカーWeb, “「公道で乗れるフォーミュラカー」だった、ヤマハ「OX99-11」”, 2024年4月5日 [33]
- 【28】 AUTO MESSE WEB, “現存数3台 新車価格約1億3000万円だったヤマハ「OX99-11」とは?”, 2023年4月9日 [35]
- [1] [2] [3] [5] [10] [13] [15] [20] [21] [25] ホンダHSV-010、マツダRX500、日産MID4…幻になった国産スーパーカーたちの墓標 – 自動車情報誌「ベストカー」https://bestcarweb.jp/feature/column/828459
- [4] [7] [8] ホンダ・HSV-010 – Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BBHSV-010
- [6] [24] [29] [30] [31] [45] 発売直前でお蔵入りになったモデルもあり? 和製スーパーカー5選 | くるまのニュース – (2)https://kuruma-news.jp/post/355111/2
- [9] 300馬力超え! ホンダ「2人乗り和製スーパーカー」がスゴかった! V6ミッドシップ×全長4.3m以下のコンパクトサイズ! 幻の「NSX後継!?」コンセプト「HSC」とは(くるまのニュース) | 自動車情報・ニュース – carview!https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/9dc1ded574cfec1a1471e55a7591c8cb7a63d91f/
- [11] [14] [16] [17] [46] マツダが作った幻のスーパーカー? 「RX500」の実物に遭遇! | マイナビニュースhttps://news.mynavi.jp/article/20240222-mazda-rx500/
- [12] [18] Mazda RX-500 – Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_RX-500
- [19] [22] [23] [26] [27] [28] MID4が「幻のスーパーカー」と呼ばれる理由!なぜ日産は開発をやめた? – COBBYhttps://cobby.jp/nissan-mid4.html
- [32] 日産: NISSAN HERITAGE COLLECTION|ニッサン MID4 (II型)https://www.nissan.co.jp/HERITAGE/DETAIL/167.html
- [33] [34] [36] [37] [41] [44] ホンダHSV-010、マツダRX500、日産MID4…幻になった国産スーパーカーたちの墓標 – 自動車情報誌「ベストカー」https://bestcarweb.jp/feature/column/828459?prd=2
☆あなたへのおススメ☆
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説