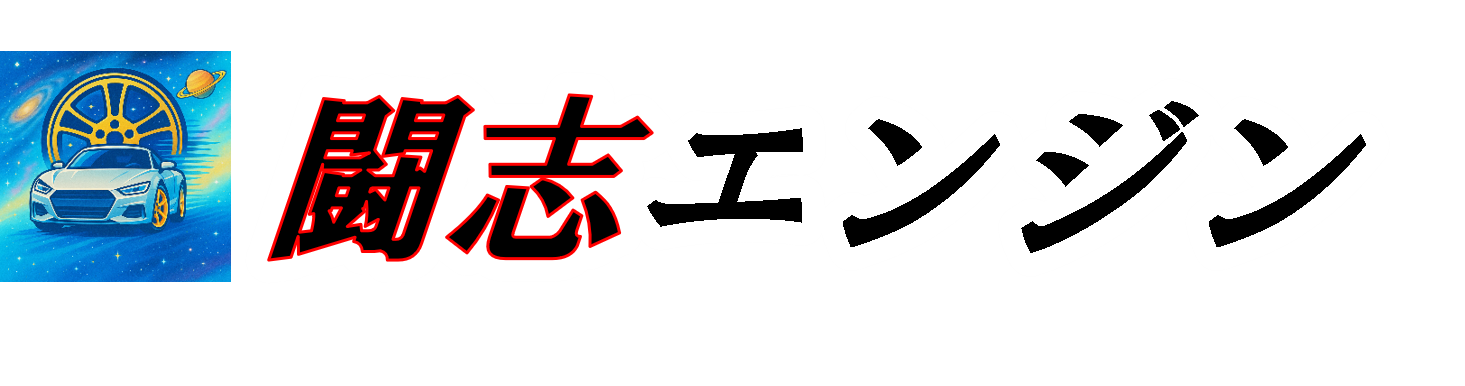【国産スポーツカーの終わり】日産GT-R生産終了の理由

本記事は広告を含みます。
長寿のR35型日産GT-Rがついに生産を終えました。終幕の背景は単一要因ではありません。騒音・排ガスや歩行者保護など法規の高度化、型式認証の更新負担、低ボリューム車の採算性、そしてR35というプラットフォームの寿命が重なった結果です。本稿で掘り下げた論点を、要点とともに改めて振り返ります。
法規制・認証要件の壁

騒音・排ガス規制強化への対応コスト
R35が最初に大きな壁に直面したのは「騒音」でした。欧州ではUN-ECE R51-03(加速走行騒音)に基づく規制が段階的に強化され、GT-Rは2022年に欧州販売を終了しています。メーカー広報も「EU/UKのドライブバイノイズ規則(No.540/2014)への適合が困難」と説明しており、ハイパフォーマンス車にとっては小さくない負担でした。日本でもR51-03のフェーズ3適用が進み、実走行条件を模した試験や追加騒音規定(ASEP)への対応が必要になります。加えて、2024年10月から国産車の車検にOBD検査が本格導入され、エミッション関連の自己診断や故障コード管理が一段と厳格化。こうした複合要件を既存パッケージで満たすには、騒音・排ガス・制御ロジックまで広範な見直しが必要となり、R35の延命コストは加速度的に増していました。 (evo, Carscoops, 環境省, obd.naltec.go.jp)
歩行者保護など衝突安全の適合ハードル
歩行者保護(UN R127)の要件も拡張され、頭部衝撃の評価領域拡大やアクティブフード等の「展開型歩行者保護システム(DPPS)」の評価手順が明確化されました。新型式は2024年7月、すべての新車は2026年7月に03シリーズ改訂へ適合が必要という欧州の運用も示され、前端構造・ボンネット下パッケージングに余裕の少ない既存スポーツカーには構造改変のハードルが高くなります。R35は設計の起点が2000年代中盤であり、衝突・歩行者保護の最新要件を満たすための大規模ボディ改修は現実的ではなくなっていました。 (interregs.com, UNECE)
型式認証・生産認可の更新期限と影響
さらに、EUのGeneral Safety Regulation(2019/2144)はAEB/ISAなどの先進安全装備を新型式(2022年)→全車(2024年)と段階適用。要件の繰り上げに伴う再型式認証や試験コストは、成熟世代の低ボリューム車には重荷です。市場別規制の差異も無視できず、オーストラリアではサイドインパクト(ADR85)で2021年にGT-Rが退場。R35をグローバルで売り続けるための認可維持は、法規の多様化と厳格化によって「割が合わない」局面に至ったと言えます。 (EUR-Lex, バイエルン州運輸省, Carsales)
ビジネス面の決断

電動化投資への資源シフトと機会費用
日産は「Nissan Ambition 2030」でカーボンニュートラルと電動化を掲げ、全固体電池(ASSB)の自社適用をFY2028に公言しています。研究開発・生産体制・調達を電動領域へ振り向けるうえで、個体車種の延命に必要な開発工数・認証コストは明確な機会費用になります。ハローカーであるGT-Rといえど、電動化の波に対しては「次章に向けた一時停止」を選ぶのが合理的でした。実際、R35の最終号車が完成した現在も「GT-Rの名は将来も生きる」とのメッセージが発せられており、ブランド軸の再投資が示唆されています。 (日産自動車グローバルサイト, 日産ニュース)
低ボリューム車の採算性と部品供給終了問題
R35は18年で約4.8万台規模の累計。手組みのVR38DETTを特徴とする生産方式は象徴的価値が高い反面、固定費回収の視点では不利です。需要が先細りする地域から順次退場し(北米は2024年に生産終了、2025年に日本で受注終了)、最終的に単一市場偏重の生産となれば、サプライチェーン維持・部材専用化のコストは跳ね上がります。電動化投資の優先順位が高まる中で、R35に追加で大型投資を行う合理性は薄れ、事業判断としての「幕引き」は必然だったと考えます。 (日産ニュース, 日産ニュース, Carscoops, カーアンドドライバー)
プロダクトライフサイクルの終着点

R35プラットフォームの老朽化と開発限界
R35は2007年登場。長寿命化のなかで空力・シャシー・制御の改良を重ねましたが、衝突・騒音・電装アーキテクチャなど「土台」にかかわる規制進化は、設計起点の古いプラットフォームには厳しくなります。18年目の2025年、栃木工場で最終号車(Premium edition T-spec/ミッドナイトパープル)がラインオフ。GT-Rらしい「走り」の本質を崩さず、最新要件を満たすには全面刷新が必要という結論に至ったとみるのが妥当です。 (日産ニュース, Motor1.com)
モデル末期の商品力・価格戦略の再検討
最終盤のR35は、NISMOやT-specなど特別仕様で価値を凝縮し、価格帯を上げつつ台数を絞る戦略でブランド価値の毀損を避けました。これは高性能車の定石で、需要の弾力性が低い熱心な層に向け、コスト上昇分を吸収する狙いです。最後を飾ったT-specは象徴色と装備で“記念碑”としての役割を担い、次世代への橋渡しを果たしたと言えます。 (Motor1.com)
マーケット環境の変化

2ドア高性能車セグメント需要の縮小
米国ではスポーツカーの販売シェアが2016年の約2%から2021年に1.5%へ低下し、2024年は前年から約13%落ち込んだとの集計もあります。セグメントの縮小はモデルサイクルや投資回収に直結し、各社の撤退・縮小を加速。たとえばChevrolet Camaroは2024年で生産終了となりました。こうした環境では、R35のようなピュアスポーツを量産で支えるのが難しくなります。 (GCBC, Carscoops, シボレー ニュースルーム)
若年層のクルマ離れ・保険/維持費の上昇
可処分所得の伸び悩みや維持費の上昇、都市部の駐車事情などが“セカンドカー的嗜好品”に不利に働いています。R35は走行性能に対し価格競争力の高い時期もありましたが、為替や原材料高、規制対応コストの転嫁で取得・維持のハードルは年々上昇。結果として、裾野拡大よりもコアファン向けの限定販売に収斂し、ライフサイクル後期の需要を細く長くつなぐ構図になっていました(本項は市場動向の一般論を踏まえた考察)。
エミッション規制時代の価値観シフト
欧州のCO₂フリート規制(2019/631)や各地域の燃費基準は、メーカー全体の平均値を重視します。高排出のハイパフォーマンス車は「平均」を押し上げ、他車での相殺や罰金リスクを招きやすい存在です。EV比率の上昇が各社のCO₂実績を押し下げている事実もあり、ラインアップ構成は電動化へと偏ります。GT-Rのような内燃ハローは“次世代の形”に改めて再定義される段階に入りました。 (IEA, 欧州環境庁)
ブランド/モータースポーツ戦略の再設計

NISMOと「フェアレディZ」の棲み分け
ハロー的役割は当面「Nissan Z NISMO」が担います。Z NISMOは420hpの強化パワートレインやエアロ・シャシーチューニングを採用し、量産スポーツの核を維持。モータースポーツ由来の知見を市販車に落とし込む“NISMOの通り道”として、ブランドの情緒価値をつなぐ意義は大きいでしょう。 (Nissan USA)
コンセプト「Nissan Hyper Force」が示す方向性
2023年のJapan Mobility Showで公開された「Nissan Hyper Force」は、GT-R的アーキテクチャをEVで描き直す提案でした。高出力モーターと先進の車両制御、カーボンコンポジットの軽量化思想——ハロースポーツを電動で成立させる青写真です。コンセプトの実装は時期尚早でも、次世代GT-Rの“設計言語”を明快に示した意義は大きいと評価します。 (日産ニュース)
ハイブリッド/電動化(e-POWER/EV)の可能性
日産は電動技術の選択肢を広く持ち、シリーズハイブリッド(e-POWER)からASSB搭載EVまでロードマップを提示。上級幹部も「GT-Rの名は将来も続く」と言及しており、電動化時代のハローに向けた準備が進みます。高応答モーター駆動と電子制御の親和性は、GT-Rの「加速とトラクション」を新たな形で再現しうる領域です。内燃の“味”をどう継承するかが次章の勝負どころになるでしょう。 (australia.nissannews.com, 日産自動車グローバルサイト)
最後に

GT-Rの生産終了は「終わり」ではなく「次章の準備」です。電動化へ資源を集中し、当面はZ/NISMOが情緒価値をつなぐ一方、Nissan Hyper Forceが示す青写真は将来のハロー像を予告します。R35が築いた性能哲学は、電動時代の制御技術と結びつくことで、新しい“GT-Rらしさ”として再定義されていくはずです。
要点
- 法規制の厳格化(騒音・排ガス・歩行者保護)と型式認証の更新負担が、R35の既存パッケージでは割に合わなくなったためです。
- 電動化への投資シフトと低ボリューム車の採算悪化により、延命開発より生産終了のほうが事業的に合理的だったためです。
- R35世代の設計限界と市場縮小を踏まえ、当面はZ/NISMOにハローを委ねつつ、Nissan Hyper Forceに示された電動ハイパフォーマンスへ軸足を移す段階に入ったためです。
参考文献
- 日産グローバルニュースルーム:R35最終号車ラインオフ、累計約4.8万台等の公式発表。 (日産ニュース)
- 欧州騒音規制とGT-R欧州販売終了の背景(UN-ECE R51-03/報道)。 (evo, Carscoops)
- 日本のR51-03運用・OBD車検の概要。 (環境省, obd.naltec.go.jp)
- EU一般安全規則(2019/2144)の段階適用。 (EUR-Lex, バイエルン州運輸省)
- 北米での生産・受注終息報道。 (Carscoops, カーアンドドライバー)
- 市場動向(スポーツカー販売の縮小)。 (GCBC, Carscoops)
- Nissan Hyper Forceコンセプト、e-POWER/ASSBの技術方針。 (日産ニュース, 日産自動車グローバルサイト)
☆あなたへのおススメ☆
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説