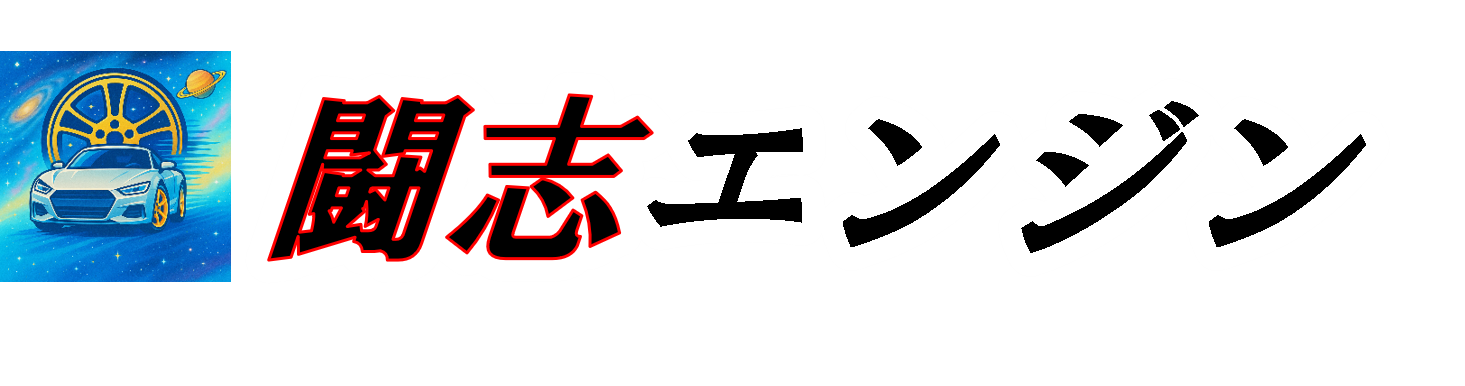【自動車の派手なウイングを紹介】一度見たら忘れられない

皆さんは自動車のウイングについてどう思いますか?見た目だけなのか、それとも機能性を追求したものか、様々なものがあると思います。そこで本記事では多種多様なウイングを装着している車について紹介します。
スカイラインR33型GT-R

1995年にR33型スカイラインは登場し、先代より性能が向上、よりスピーディーなものに仕上がりました。この車の特徴の一つが角度調整機能が付いたこのリアスポイラーです。角度は水平、6度、12度、18度の4段階であり、高速で走るサーキットのコーナーではこの効果が大きく発揮されます。

R32型スカイラインGT-Rのような固定式リアスポイラーも良いですが、サーキットに合わせて好みのセッティングできるリアウイングもスポーツカーとして面白いギミックです。
三菱GTO

1990年に登場した三菱GTOも派手なリアウイングをもつ車として有名です。最高出力280psを発生する3.0リッターV6ツインターボとその自然吸気版の2種類をもち、ツインターボ仕様には独ゲトラグ社製の5MT自然吸気仕様には5MTと4速ATが採用されました。

そして1998年に登場したマイナーチェンジにより、そこで特徴的だったのが大きなリアウイングでした。
トヨタ80スープラ

1993年にA80スープラは登場し、大型ウイングは印象的だと思います。先代スープラの直線的なデザインとは対照的で流麗なカーブをもったグラマラスボディーに合うような大きなカーブのウイングがオプションで用意されました。

実は純正だったというのが意外でしたね。また何故こんなに背が高いかというと後方見えやすくするためだからと言われています。
フェラーリF40

1980年代に入ってから巨大で派手なウイングと言われて印象的なのがフェラーリ40周年記念モデルであり「公道を走れるレーシングカー」というコンセプトで開発されたF40でしょう。F40のリアウイングはコンセプト通りサーキット専用のレーシングカーのようでした。

F40の外装パネルと同様にケブラー製でありリアのキャノピーと一体の構造になっています。また軽量化のため塗膜は最低限の厚みとされており、オリジナルの塗装が残されている車体ではカーボンファイバーが確認されるようです。
メルセデス・ベンツ190E 2.5-16 エボII

メルセデスはBMW M3に対抗するため190E 2.5-16エボリューションを開発しました。そして1990年に大型リアスポイラーを装着して登場したのがエボIIでした。

控えめなエボIのウイングに対しエボIIピュアなレースカーのようです。またウイングは見かけだけのものではなく風洞実験においてはCd値0.29を達成しながらさらなるダウンフォースを得ていました。
スバル・インプレッサ22B

スバル・インプレッサは長年のモデルですがその中でも注目されているひとつの車種として22Bが挙げられます。この車は派手なウイングが装着されておりレースカーのようです。このウイングはエッジが可動式となっており、その角度を調整することができます。

実際にはWRCのラリーカーのものと異なるデザインとなりましたが400台の生産枠は24時間で埋まってしまうほどの人気車でした。
マツダランティス

ランティスはマツダが製造・販売していた車でクセの強いウイングが特徴的です。搭載されたエンジンは2種類でどちらも自然吸気を採用しています。1.8リッターの直列4気筒DOHC「BP-ZE型」と2リッターのV型6気筒DOHC「KF-ZE型」が用意されました。

1.8リッターエンジンは初代ロードスターにも搭載されたエンジンで自然なフィーリングが特徴。一方、2リッターのV6エンジンは振動を抑えるバランサーシャフトを搭載した贅沢で凝った構造をしています。他にも4ステージの可変共鳴過給システムVRIS、水冷式オイルクーラー、炭素鋼鍛造クランクシャフト、ピストン冷却用オイルジェットなど普通の車では思えない高品位な構成となっています。そしてこの車の目玉であるウイングはマツダスピード製のものです。非常にインパクトがありますが、空力を考慮するとなるべく高く、そして後ろ位置にスポイラーがあるこの形状は有効的であると思われます。
パガーニ・ゾンダR

このモデルはRの名称が示す通り、サーキットで走らせることを想定した車です。しかし、驚くべきことに標準のゾンダと共通パーツは少量であり、わずか1割程度でした。Rの特徴は可変リアウイングです。

これによる空力性能のおかげニュルでは6分47秒という記録を樹立しました。そして2億円の値がつけられ、15台が販売されました。
プリマス・ロードランナー・スーパーバード

ロードランナー・スーパーバードは1960年代にダッジ、フォード、マーキュリーなどがエアロ競争を繰り広げた時代の産物です。プリマスはこのモデルをホモロゲーション用として位置付けていました。この派手なウイングは専用設計であり空力性能を発揮し、当時のアメ車文化を支えました。

なお、このウイングは風洞実験によりルーフと同じ高さでも性能が発揮できると判断されましたがトランクを開けることを考慮してルーフよりも高く設計されました。
プリメーラ・オーテックバージョン

初代プリメーラはFF車初のフロントマルチリンクサスペンション、数多くの制約の中で生み出した美しいスタイリング、日本の街中でちょうど良い5ナンバーサイズ、それに見合った2リッターの直列4気筒DOHCの素直な自然吸気エンジン、十分な広さを持つ4ドアセダンパッケージングなど当時の日産も十分に感じさせる車になっています。

その中でもオーテックバージョンはプリメーラの良さを活かしたレベルの高いモデルでありアナログな内燃機関と駆動系のチューニングを施し、ボディーやエクステリアまで拘ったメーカーチューンドとなっています。エアロも大型ウイングをはじめスポーティーさを極めておりFF版スカイラインと言っても過言ではありません。
ホンダ・シビック・タイプR(2015)

ホットハッチの第一線から離れていたホンダは3年ぶりにシビック・タイプRを開発しました。FK2型はパワーとその速さに加え、その大型リアウイングが特徴となりました。機能性を第一に設計され、確かなダウンフォースを発生します。これがライバルとの明確な差別化に貢献し新たなホンダを得ることができたのではないでしょうか。

またこのウイングはFK8型にも引き継がれ、さらなるパワーとダウンフォースを獲得しました。このウイング形状は世界ツーリングカー選手権で使われたマシンから得られたデータを用いて設計されています。ルーフ後端に取りつけられたボルテックス・ジェネレータはより多くの空気をウイング表面に導く性能があります。
フォード・シエラRSコスワース(1985)

この車のウイングも特徴的な見た目をしています。シエラは3ドアハッチのリフトに対応するため高い位置にウイングを取り付けることになりました。

当初はフォード経営陣から不評とされましたが、時速240キロを超える速度に対応するために必要不可欠なウイングでした。事実、RSコスワースは公道でもサーキットでも活躍することができました。
・ランボルギーニ・カウンタック(1978)

カウンタックの初期型となるLP400はコンセプトカーに一番近いルックスであり直線的なシンプルさが際立っています。しかし、年代を重ねるごとに形状は変化していきガンダムのようなゴツゴツしたデザインへとなりました。そんなカウンタックの中でも1978年のLP400Sで採用されたV型ウイングはいかにもスーパーカーらしいエアロとなりました。またウイングは脱着式となっており用途や気分に応じて取り外すことができました。

しかしウイングを取りつけた状態では高速域のスタビリティーが向上するものの最高速は抑制されてしまいました。LP400Sの場合、リアウイングなしでは時速290キロであったのに対しウイング装着時では時速16キロ程度低い数値となっています。またカウンタックはデザイン的に印象のあるものですが空力的には問題あり高速になると揚力性があることが発覚しました。そのため対策としてフロントにウイングが付けられました。
まとめ
さて今回の記事はいかがでしたか?国産車をはじめ世界中の車を見ていると様々なウイングがあって、自動車の世界がさらに深まったと思います。
お知らせ
本サイトを見て頂きありがとうございます。当サイトでは自動車関係の記事を投稿しています。またYouTubeちチャンネル「自動車好きのダイスマン」としてもSNS活動をしているので、興味のある方はそちらも是非見てください!
▼YouTubeチャンネル
http://www.youtube.com/@tv6061
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説