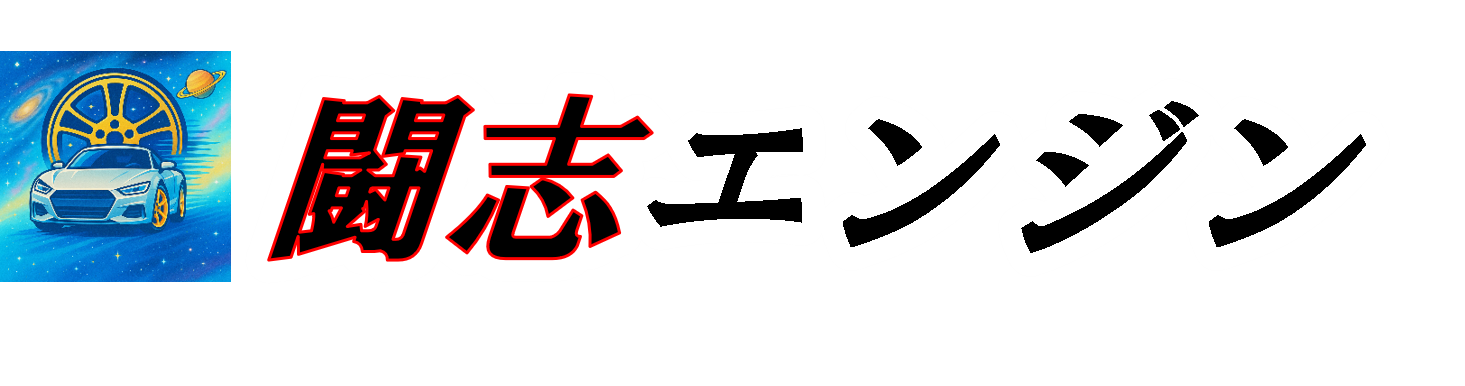初代ヴィッツは何が良かったのか?

本記事は広告を含みます。
トヨタのコンパクトカー「ヴィッツ」の初代モデルは1999年1月に発売が開始されました。それまでの同社のエントリーモデルは排気量1.3Lの「スターレット」でしたが、当初1Lのみでスタートしたヴィッツは、事実上そのスターレットの後継モデルとしての役割を持って生まれました。
不況の時代

1999年といえば平成不況の真っただ中と思います。世界中のコンピューターが誤作動を起こして生活が成り立たなくなったり、ノストラダムスの大予言が的中して人類が滅亡するのではないかとも言われていました。もちろん自動車業界も大きな転換期を迎えており、スポーツカーブームからファミリー層に着目した時代でもありました。令和現在、ネオクラと称される車たちがなくなってしまったことも記憶にあると思います。車のトレンドもミニバンや小型車など必要性が主でした。98年の普通車販売ランキングではカローラ、デミオ、マーチ、スターレットがあり、実用的な小型車が大半を占める形です。当時のコンパクトカーはもちろん魅力的なモデルもありましたが、今のように最先端の技術がなかったため、どちらかといえばコスパの良さを理由に選ぶことが多かったように思います。そんな自動車にとっても波乱の時代に生まれたのが初代ヴィッツです。
ヴィッツとは?

では、ここでヴィッツについてシリーズを踏まえつつ概要を紹介します。あらためてヴィッツ(Vitz)はトヨタ自動車が販売していた1.0 L – 1.5 Lクラスのハッチバック型乗用車です。日本国内では一貫して新旧ネッツ店でのみ取り扱われていた看板車種となっていました。国内では「ヴィッツ」、国外では「ヤリス」と名称が区別されていましたが、2020年2月発売の4代目から車名が日本国内・国外ともに「ヤリス」に統合されました。初代は1.0 L 直列4気筒DOHC16バルブ1SZ-FE型のモデルのみで、Aセグメントの市場に登場しました。1999 – 2000日本カー・オブ・ザ・イヤーをプラッツ・ファンカーゴとともに受賞、欧州カー・オブ・ザ・イヤーも受賞しました。それまで販売台数で上位にあったカローラを上回る販売台数となり、日本国内外に影響を与える車となりました。

続いて2代目は2005年に登場し、欧州でも2代目ヤリスとして発売されました。プラットフォームを刷新し、ボディーサイズが一回り大きくなり、全幅は5ナンバーサイズとしてはほぼ上限の1,695 mmとなりました。また、衝突安全性が大きく強化されています。次に3代目はCd値0.285の優れた空力性能を実現し、低燃費と高速走行における走行安定性を実現したモデルとして登場しました。先代に引き続き、日本仕様は5ドアのみ、3ドアは日本国外仕様にのみ設定されています。前席にはホールド性の高い新骨格のシートを採用、後席は全長の拡大により室内長も拡大されたことで足元のスペースが拡がり快適性が良好なりました。インテリアでは初代・2代目で採用されていたセンターメーターを廃止してオーソドックスなアナログメーターに変更されました。
初代ヴィッツのデザイン性

では、初代ヴィッツのデザインを見ていきましょう。エクステリア・デザインはギリシャ人デザイナーの手によるもので、スターレットなどのトヨタ製コンパクトカーはもとより、国内外で類を見ないアグレッシブさを感じさせるデザインになっています。
外観

当時としてはかなり斬新なもので、ボンネットとフロントガラスが段差なくなめらかに繋がっています。そしてリアエンドまでスムーズに続くワンモーションフォルムで、ラウンド基調の一体感が感じられます。従来の2ボックススタイルとは異なりで革新的なスタイリングです。フェンダーも張りのある造形で、シンプルさとおしゃれさがバランスよく融合したデザインがボディーの雰囲気と合致しています。後ろ姿も特徴的で、締まったような凝縮感が車両イメージとマッチしています。全体の雰囲気はころころと丸くてソフトですが、シャープなラインが大胆にボディーサイドを流れていることで、外観をぐっと引き締めています。ふっくらした基本シルエットに程よい緊張さをもたらすアクセントです。このプレスラインはアンダーボディーの張り出しももたらしており、コンパクトながらどっしりした感じもしています。丸くて可愛らしいのに安定感や上質感もあるバランス良いデザインが、それまでの国産コンパクトカーにはなかった新時代を予感させたのでしょう。

ヴィッツとは「活発に動く」という意味するドイツ語に由来するようです。このデザインはトヨタの自信作で意欲的に作られました。本社によるデザイン案とベルギーにある開発拠点によるデザイン案を欧州のユーザーに対して調査し、結果的にベルギー拠点のデザイン案が採用されました。この案はギリシャ人デザイナーによるもので、「ヨーロッパ的で力強く、飽きられることのないクリーンなデザインを目指した」とコメントしています。ヴィッツのデザインには日本ではなく、海外テイストが込められたことが分かります。
インテリア

エクステリア以外も相当力が入っており、インテリアの注目箇所はセンターメーターでしょうか。現在では見慣れたレイアウトですが当時としては珍しく、ドライバーの視界移動が少なくて済むというメリットも相まって高評価だったようです。また、インパネ周りには多数の収納が設けられており、これも些細なことかもしれませんが日常使いとして大きなポイントです。外観に合わせてデザインされたインテリアの雰囲気もふんわりとしたイメージがあり、室内空間も広くて、居住性も申し分ないレベルでした。高めに設定された全高とロングホイールベースにより、大人5人が長時間乗車する事が可能でした。
エンジン
さらにエンジンも新規開発され、スターレット用の1.3Lエンジンなどを流用すればよかったのでは?と思いますが、トヨタはリッターカーに拘りました。新開発のエンジンは1L直列4気筒DOHCの1SZ-FE型で、最高出力70PS、最大トルク9.7kgmの軽量ボディーには必要な性能を備えていました。トランスミッションは5速MTと4速トルコン式ATが用意され、駆動方式は当初FFのみでした。プラットフォームも新設され、剛性と衝突安全性が向上、サスペンションも見直されたことから直進安定性も高かったようです。このことから、どの視点から見ても隙のない渾身の自信作であることが分かります。
初代ヴィッツの評価

発売当初、初代ヴィッツは大きな反響を呼び、日本でも欧州でもヒットしました。国内ではデミオやキューブ、マーチらを抑えて15万台以上販売されました。欧州でも半年で約15万台受注し、これはスターレット時代の約5倍にあたる売り上げです。また日本カーオブザイヤーと欧州カーオブザイヤーのダブルタイトルを受賞したことからも、国内外での評価が高かったことが容易に想像できます。燃費に関してはで22.5km/Lと高レベルの低燃費を誇り、価格は83万円からとリーズナブルでした。そのため高い経済性から日本のみならず、海外でもヒットしました。滑り出し好調だった初代ヴィッツは1999年8月にはラインナップを拡充しました。まず88馬力を発揮する1.3リッター直列4気筒エンジンを搭載したモデルが追加、余裕のある走りを実現し、同時に4WDも設定されました。また、1.3リッターモデルに先んじて発売された「ユーロスポーツエディション」があり、上級グレードの「U」に欧州仕様のサスペンションとスタビライザー、アルミホイールなどを備えたスポーティーなモデルとなりました。このモデルはインターネットのみの販売というユニークな方法になりました。このことから初代ヴィッツをベースとした車種が登場し、後年にはスポーツグレードが追加されるなど、初代ヴィッツは幅広い層に受け入れられ、多方面で活躍することになります。
海外での活躍
90年代、欧州地域は小型車の比率が高く、統計では全自動車に占める小型車比率がなんと6割以上も占めていました。また欧州における当時のトヨタ車シェア率は極めて低かったため、巨大市場である欧州スモールカーカテゴリーにおいて、この状況を対策すべく新たな車種が必要になりました。それが、初代ヴィッツだったのです。
最後に
以上のことから、人気になった初代ヴィッツはコンパクトカー市場を活性化させ、多くの市場価値を生み出しました。そして2001年に登場したホンダ・フィットは恐らく初代ヴィッツの影響を受けていると思われ、コンパクトカー業界では新たな人気車種になりました。また、マーチやデミオも一新され、どのメーカーもコンパクトカーを意識したモデルを販売させました。そのため時間が経過するごとにヴィッツは少しずつコンパクトカーとしての順位を下げましたが、現在ではヤリスがヒットし、再び活気を取り戻しています。国内外で求められる性能を満足させるものであり、欧州でも要求される環境基準や高速安定性などのニーズに対しても高いレベルで応える内容の車でした。そしてコンパクトカーとしてのイメージを新しくしたポイントは欠かせません。それまではどこか卑屈で窮屈だったイメージだったコンパクトカーですが、乗るたびに楽しくなるような存在として生まれ変わらせました。自動車業界に影響を与え、ベンチマークとなってコンパクトカーの存在レベルを引き上げたことは初代ヴィッツの最大の功績と言っても過言ではありません。現在、環境基準が厳しくなり、内燃機関の存在について疑問視されるようなこの時代において、小さなエンジンを積んだヤリスのようなコンパクト車の存在はさらに高まっていくかもしれません。
YouTubeチャンネルのお知らせ
本記事をお読みいただきありがとうございます。本サイトは車関連の記事を投稿していますが、Youtubeでも投稿を行っています。興味のある方は是非、YouTubeチャンネルもご覧になってください。
最新記事はこちら⇩
- 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
 コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド!
コンパクトなのに広い――そんな一言で語られがちなトヨタ・ルーミーですが、実際の満足度を左右するのは「内装の作り… 続きを読む: 【トヨタ・ルーミーの内装は本当におしゃれ?】評判・実用性・カスタム術を完全ガイド! - 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
 トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証
トヨタ・ライズは「ダメ」と言われることがありますが、実態は“価格とサイズに対して何を期待するか”で評価が割れや… 続きを読む: 【トヨタ・ライズは本当にダメなのか】評判と実態を検証 - 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
 カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説
カローラの名を冠しながら、アクシオは「新車でも中古でも手が届きやすいセダン」として語られがちです。実際、トヨタ… 続きを読む: 【カローラアクシオが安い理由】とリアルな評判を徹底解説